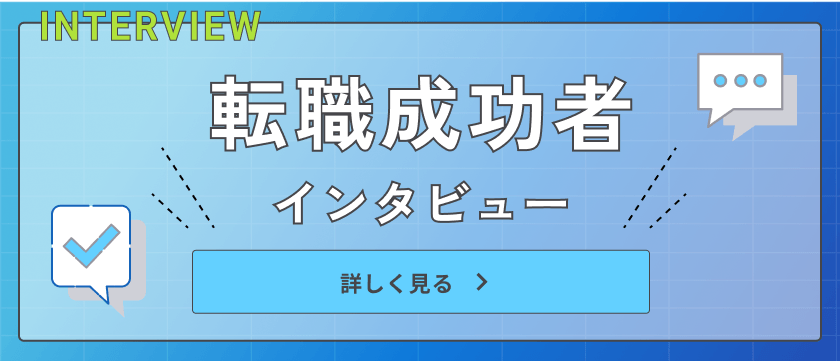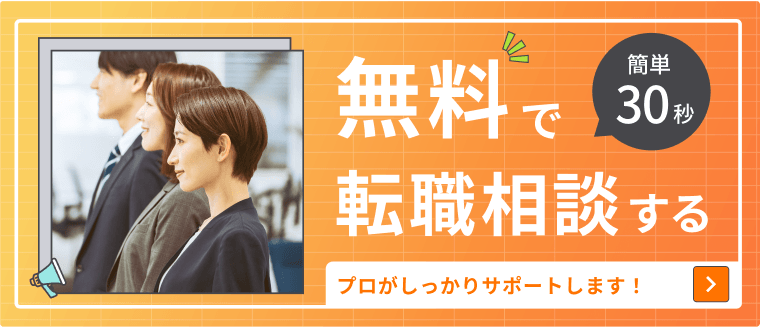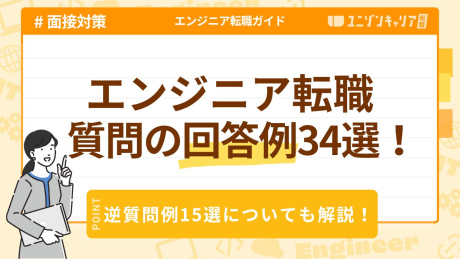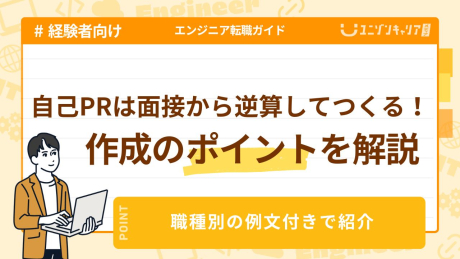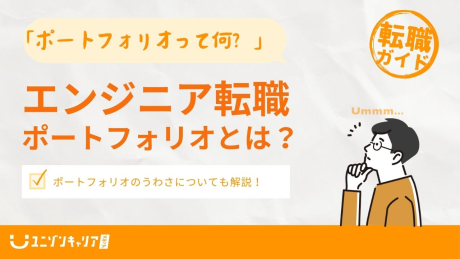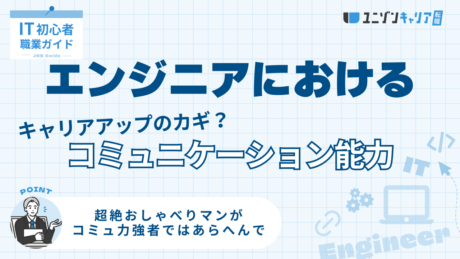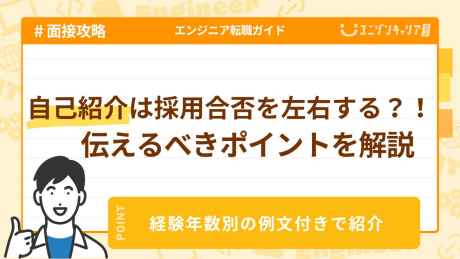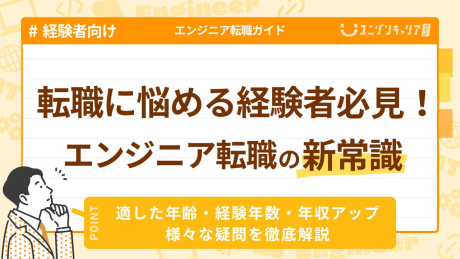
最終更新日:2026.02.10
ITエンジニア経験者の面接は技術質問を対策せよ!職種別の質問&回答集178選

IT業界を本音で語る「ユニゾンキャリア編集部」真心です。

本記事のトピックスはこちら
- エンジニアの面接対策はどうすればいいの?
- エンジニアとして経験があるのに落ちる人の特徴は?
- 効果的な面接練習方法が知りたい!
IT人材不足の影響からエンジニアの求人は増加しており、求職者優位の状況です。エンジニアとしての経験があれば、未経者と比較してもより転職活動は有利に進められます。
しかし、転職を考えている人の中には面接に苦手意識を持っており、「面接対策をどうしていいかわからない」というご相談を数々受けてきました。
記事の要約
本記事では、エンジニアの経験者を対象に、面接対策で重要な「スキル」「人柄」「再現性」の3つの要素から面接での落とし穴や職種別の技術質問と効果的な練習方法まで網羅的に解説します。
1.エンジニアの面接で対策すべきポイント
エンジニアの面接は対策が全てといっても過言ではありません。まずは「なぜ対策が必要なのか」「どのような対策が必要になるのか」を解説します。
- 採用の視点やニーズを紐解く
- 自身の実績とスキルを証明せよ
- エンジニアの面接での服装
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
1-1.採用の視点やニーズを紐解く
企業によって求める人物像は異なるため、応募先企業それぞれの採用ニーズを理解し面接に望むことが重要です。
どれだけ面接の準備ができていて良い発言ができたとしても、企業が求める人物像とマッチしなければ面接の通過は難しく、不採用になります。
もちろん、企業が求めている人物像の要素すべてを満たす必要はありませんが、多くの要素に合っていれば採用の可能性は高くなります。また、求める人物像やプロジェクトの内容を把握できていれば、自身の強みをアピールでき、企業が求める人物像とマッチし通過する確率は高くなります。
企業の採用ニーズを理解するために、以下の情報などから必要とされるスキルセットや強み、経験など分析を行います。
- Webサイト
- 求人情報
- 経営者のインタビュー記事
- 企業のSNS
企業研究を徹底的に行い、採用ニーズを満たす自己PRを準備し面接に臨みます。
面接では自分が言いたいことを発言するのではなく、企業の採用ニーズを満たした内容を考え発言することが重要です。
1-2.自身の実績とスキルを証明せよ
エンジニア経験者の面接では、企業にとって即戦力となれるスキルを持っているという証明が必要です。そのため、自身の実績やスキルを具体的に示すことが重要です。
実績とスキルを証明することができれば、採用担当者に自分の価値を伝えられます。
自分の実績やスキルを証明するために「〇〇のプロジェクトに携わりました」「エンジニアとして〇年間働きました」など安易な回答だけでは伝わりません。
スキルシートで提出した、過去のプロジェクトでの成果やコードサンプル、資格などを面接で深堀りを行い、具体的にどのようなことをしたのかを述べることで企業側に伝わりやすくなります。
そのためには、ポートフォリオやGitHubアカウントを整理し、自身の実力をアピールできるように話す内容の準備が必須です。具体的な数字や実績、ストーリーを交えて受け答えができれば、信憑性が高く企業からの信頼を得られます。
また、「現在のスキルからどのように仕事に活かすのか」や「現在、何に取り組んでいて、どのような方向性でキャリアを進める想定なのか」などを伝えられれば、採用担当者も自社にとって利益があると判断できます。
経験者の転職は即戦力が求められるため、あなたが企業に入ることで「どのような利益をもたらせることができるのか」を証明することが面接通過のポイントです。
1-3.エンジニアの面接での服装
当然ですが、面接時の服装は面接を通過するうえで重要です。一度、転職を経験したことで、面接に慣れているから細かな配慮に気付かないこともあります。
気を使えばできる服装のシワが多い、汚れがついているなど第一印象が良くなければ、どれだけ実績や高いスキルを保持していても不利です。まずは、マイナス要素を徹底的に排除することが大切です。
基本原則として、服装はスーツで面接に臨みます。転職の面接は新卒面接とは違い、リクルートスーツはNGなので、スーツがなければ、紺色やグレーなどの色で新調してください。
当日の面接前に準備するのではなく、早めに着いてトイレなどの施設で事前に身だしなみをチェックすることが大切です。また、オンライン面接の場合は、事前にzoomやGoogle meetなどのミーティングツールを使って映り具合を確認することはマナーです。
面接での第一印象の割合は見た目で「メラビアンの法則」によると、約55%のインパクトがあるとされています。服装なんかで悪い印象を与えてしまうのは、非常にもったいないので、気を抜かずに準備するように心掛けてください。
2.エンジニアの面接はスキル・人柄・再現性がみられる
エンジニア経験者の面接では「スキル」「人柄」「再現性」の3つを満たすことが重要になります。なぜ、この3つが重要なのか?具体的な内容について詳しく解説します。
- エンジニアはスキルが市場価値
- プロジェクトやチームとの調和は人柄に
- ポジションの募集に応える再現性を
2-1.エンジニアはスキルが市場価値
エンジニアの面接では、候補者のスキルを見極めることが重要です。面接官は、候補者が特定の言語やフレームワークに精通しているか、リーダー経験があるかなどを確認します。
面接では、候補者のスキルが企業の求めるスキルにマッチしているかを判断します。
例えば、企業側が「Python」を使えるスキルを持っている人材を採用したいと考えているのに、候補者がPythonを使えないのでは不採用となる可能性が高くなります。
また、面接官は候補者が常に新しい技術を学びスキルを向上させる意欲があるかどうかも重要視します。優秀なエンジニアは、常に自己研鑽を怠らない傾向があるからです。
面接では、候補者のスキルを適切に評価し、企業の求める人材像にマッチしているかを判断します。候補者のスキルのレベルによって、採用の可否が大きく左右されるため、エンジニアの面接ではスキルの見極めが非常に重要な要素となります。
2-2.プロジェクトやチームとの調和は人柄に
エンジニアの面接では、候補者の技術的なスキルだけでなく、チームワークやコミュニケーション能力などの「人柄」も重要な評価ポイントとして見ています。
面接官は、候補者が過去のプロジェクトでどのようにチームに貢献したかを聞くことで、協調性やリーダーシップを評価します。
「問題点をまとめて修正指示を行った」「率先してチームの進捗を確認して状況報告を適時行った」など具体的な成功例を紹介できれば、チームプレイヤーとしての能力をアピールできます。
一方で、面接中に「自己都合な話ばかりしている」「感情的になる」「ルールを守らない」といった印象を与えると、協調性がないと判断され、不採用になるリスクが高くなります。
面接官は、候補者を採用することでチームにトラブルが発生するかどうかを見極めようとしています。そのため、面接ではコミュニケーション能力やチームワークを重視されます。
技術的なスキルだけでなく、チームプレイヤーとしての自覚を持ち、コミュニケーション能力をアピールすることが必要です。
2-3.ポジションの募集に応える再現性を
求められるスキルのポジションに自身のスキルがマッチしているか、ポジションの募集に応える「再現性」が重要です。
転職は即戦力となる人材を求められているため、自社が求めている人材やスキルを保持していなければ教育コストがかかるため不採用となることもあります。
面接では、求人情報に記載された要件に自身の経験が当てはまるかどうかを説明します。そのため、自身がこれまでにエンジニアとして磨いてきたスキルや経験の棚卸しを行い、求人との整合性を確認します。
もし、自身のスキルと経験が転職先企業とマッチしていなければ「どのように活かすのか」「どのように企業に貢献できるのか」を考えてみてください。
SIerや自社開発などの転職の採用は言い換えればポジションを埋めるための採用であることが大半です。また、SES企業においても高スキルであれば、単価が高くなります。
自身がそのポジションを埋められるスキルや経験も持っていると採用担当者に伝われば、面接を通過する確率は高くなります。
3.エンジニア面接の質問で聞かれる3つのこと
エンジニア面接の質問で聞かれることを理解しておき、準備を行えば本番の際に慌てることもありません。面接でよくある質問についてまとめました。
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
3-1.自己紹介は面接官への話題提供
「自己紹介」は面接官との対話の入口であり、必ず行う必要があります。
自己紹介は基本的にこれまでの業務内容の話ですが、重要なのは面接官に拾って欲しい印象的なエピソードを提供することで面接官に話題を提供できるという点です。
そのため、ダラダラと話す必要はなく、テーマを絞って伝えたい印象や次にくる質問を想定しながら自己紹介をします。逆に長々と話すと話がまとまっていないビジネススキルの低い人材だとみなされてしまいます。
就活では約1分なんて言われますが、転職の場合は1分〜3分ぐらいが面接における自己紹介の想定時間です。文字数にすると約300文字〜1,000文字程度になるので原稿を用意して準備をしてください。
※ちなみにこの章3-1で約600文字ぐらいになるので、このぐらいの文字数を書き起こすとちょうど良いという印象を持っておくと良いです。
自己紹介の原稿を準備したら、見ないでもすらすらと話せるように練習を重ねます。
注意したいポイントとして、原稿をそのまま覚える必要はないという点です。すべて覚えようとすると緊張したときに細かなことが気になってしっかりと話せなくなります。
そのため、話の流れが合っていて録音を聞き直した時に違和感がないことが最も重要です。
3-2.技術質問で採用とポジションが決まる
エンジニアは原則技術職です。そのため、スキルや経験など技術質問で採用とポジションが決まります。回答は採用の可否に直結するため、重要な質問です。
技術質問は応募者の実務能力を測るために行われる質問であり「過去のプロジェクトでの問題解決事例」や「得意な技術領域」について説明します。
予想される技術質問をリストアップし回答を準備しておくことで、質問に対して慌てることはありません。
また、技術質問のなかには「答えがわからない」ものもあるかもしれません。しかし、分かりませんと伝えるのではなく、どのような解決策があるのかを伝えてください。
技術質問は自ら解決策を導く能力も見られています。なぜなら技術質問は正解が1つとは限らないからです。自分のエンジニアとしてのスキルや経験を頼りに考えてみてください。
技術質問は自社が求めるスキルを持っているのかを確認するためでもあり、採用側にとって重要な項目です。
3-3.逆質問で意欲をアピールせよ!
面接では終わり際に必ずといっていいほど、逆質問を求められます。
逆質問は自身の意欲を示す良い機会であり、適切な質問を行えれば「企業研究の徹底さ」と「入社意欲の高さ」を示すことができます。
一方で、ありきたりな質問や調べればわかる質問は入社意欲が低いと見なされ、不採用となることもあります。
「プロジェクトの詳細」や「技術的な取り組み」などについて質問してください。
逆質問は事前に質問内容を考えておき、面接の流れに合わせて自然に質問します。最低でも5個程度は考えておき、面接の内容で話した内容と被らないものを選びます。
面接で説明されているにも関わらず、同じ内容を質問するのは面接官からすれば、話を聞いていないとマイナスな印象を与えてしまいます。
逆質問は企業への興味を示す機会であるため、マンネリ化した質問ではなく企業側が聞かれて嬉しい質問を用意するのがポイントです。
4.開発エンジニア職種の怒涛の技術質問72選
開発エンジニア職種では4種類の技術質問を掲載しています。
- SE・プログラマーの技術質問18選
- フロントエンドエンジニアの技術質問18選
- バックエンドエンジニアの技術質問18選
- 組み込みエンジニアの技術質問18選
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
4-1.SE・プログラマーの怒涛の技術質問18選
SEやプログラマーで聞かれる技術質問は以下の通りです。
- オブジェクト指向の3大要素を具体例で説明してください
- MVCパターンとMVPパターンの違いは何ですか
- 例外処理の重要性と実装方法について話してください
- Gitでのブランチ戦略はどのように決めていますか
- 単体テストと統合テストの違いを教えてください
- コードレビューでよく指摘される点はありますか
- よく使うデザインパターンとその使用例は何ですか
- コードの保守性を高めるために何を実践していますか
- 技術選定時に何を考慮しますか
- パフォーマンス改善に取り組んだ経験はありますか
- ボトルネックの特定から改善までどう進めますか
- スケーラビリティを考慮した設計のポイントは何ですか
- 大規模システムの設計から実装まで主導した経験はありますか
- マイクロサービスアーキテクチャの設計経験について聞かせてください
- CI/CDパイプラインの構築・運用経験はありますか
- 技術的な意思決定はどのようなプロセスで行いますか
- チームメンバーのスキルアップ支援はどう行っていますか
- 新技術導入時のリスク評価はどう行いますか
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
● オブジェクト指向の3大要素を具体例で説明してください
オブジェクト指向の3大要素は「カプセル化」「継承」「ポリモーフィズム」です。カプセル化は、データとそれを操作するロジックを一つにまとめ、内部を隠蔽することです。
例えば「自動販売機」クラスは、「お金を入れる」という操作のみを公開し、内部の「在庫数」データには直接触れさせません。これにより安全性が高まります。
継承は、既存クラスの性質を新しいクラスが引き継ぐ仕組みです。「動物」クラスを継承して「犬」クラスを作れば、「犬」は「食べる」機能を引き継ぎつつ、「ワンと鳴く」という独自の機能を追加できます。コードの再利用性が向上します。
ポリモーフィズム(多態性)は、同じ命令でもオブジェクトによって動作が変わることです。「犬」と「猫」に「鳴け」と命令すると、それぞれ「ワン!」「ニャー」と異なる動作をします。これにより柔軟なプログラムが書けます。
● MVCパターンとMVPパターンの違いは何ですか
主な違いは、ViewとModelの関連性です。MVCでは、ControllerがModelを更新した後、ViewがModelを直接参照して画面を描画します。そのためViewとModelが密結合になりがちです。
一方、MVPでは、PresenterがModelからデータを取得・整形し、Viewに描画を「指示」します。
ViewはPresenterの指示に従うだけでModelを直接参照しないため、ViewとModelの分離がより徹底され、UIロジックのテストがしやすくなります。
● 例外処理の重要性と実装方法について話してください
例外処理は、予期せぬエラーでプログラムがクラッシュするのを防ぎ、システムの堅牢性を高めるために重要です。
例えば、ファイル読み込み時にファイルが存在しない場合、エラーを適切に処理することで、ユーザーに状況を伝えたり、代替処理を行ったりできます。実装は、多くの言語でtry-catch-finallyブロックを使います。
tryに例外の可能性がある処理を、catchにエラー発生時の処理を、finallyに成功・失敗に関わらず必ず実行する処理(リソース解放など)を記述します。
● Gitでのブランチ戦略はどのように決めていますか
プロジェクトの規模やチームの体制に合わせて決めます。一般的には、main(リリース用)、develop(開発用)の主要ブランチを置き、機能追加はdevelopから切ったfeatureブランチで行うGit-flowを基本とします。
これにより、安定したリリースと並行した機能開発を両立できます。
小規模なチームやプロジェクトでは、mainブランチから直接featureブランチを切る、よりシンプルなGitHub Flowを採用することもあります。
● 単体テストと統合テストの違いを教えてください
単体テストは、関数やクラスといったプログラムの最小単位が、個々に正しく動作するかを検証するテストです。他の部分から隔離して行います。
一方、統合テストは、複数のユニットを組み合わせて、それらが連携して正しく動作するかを検証するテストです。
例えば、ユーザー登録機能において、「メールアドレス形式を検証する関数」のテストが単体テストで、「フォーム入力からDB登録まで」の一連の流れをテストするのが統合テストです。
● コードレビューでよく指摘される点はありますか
主に3点あります。1つ目は命名の分かりやすさです。変数名や関数名が処理内容を的確に表しているかは、可読性に直結するためよく指摘されます。
2つ目はロジックの複雑さです。ネストが深すぎる、一つのメソッドが長すぎるなど、処理が追いづらいコードは修正を求められます。
3つ目はエラーハンドリングの考慮漏れです。予期せぬ入力や外部エラーに対応できる設計になっているかは、堅牢性の観点から重要視されます。
● よく使うデザインパターンとその使用例は何ですか
Strategyパターンをよく使います。アルゴリズムをカプセル化し、動的に切り替えるパターンで、例えばECサイトの送料計算で「通常配送」「クール便」「地域別」といった複数の計算ロジックを、状況に応じて差し替える際に活用します。
また、インスタンス生成を柔軟にするFactory Methodパターンや、唯一のインスタンスを保証するSingletonパターンも、設定管理などで頻繁に使用します。
● コードの保守性を高めるために何を実践していますか
SOLID原則を常に意識して設計・実装しています。特に、クラスやメソッドの責務を一つにする「単一責任の原則」と、具象ではなく抽象に依存する「依存性逆転の原則」を重視しています。
これにより、変更の影響範囲を限定し、コンポーネントの結合度を下げています。
また、誰が読んでも理解できるよう、処理の意図が伝わる命名を心がけ、複雑なロジックにはコメントを残すようにしています。
● 技術選定時に何を考慮しますか
主に4つの観点を考慮します。
1つ目はプロジェクト要件との適合性で、パフォーマンスや機能要件を満たせるかが最優先です。
2つ目はエコシステムの成熟度で、ドキュメントの豊富さやコミュニティの活発さを評価します。
3つ目はチームのスキルセットと学習コストです。
4つ目は長期的な運用・保守コストで、ライセンスや将来性も考慮し、総合的に判断します。
● パフォーマンス改善に取り組んだ経験はありますか
前職のECサイトで、商品一覧ページの表示に平均3秒かかっていたものを、1秒以内に改善しました。
APMツールでボトルネックがDBクエリにあると特定し、N+1問題の解消、インデックスの追加、そして更新頻度の低いデータに対するキャッシュ(Redis)の導入を行いました。
結果、平均表示速度を約800ミリ秒まで短縮でき、ユーザー体験の向上に貢献しました。
● ボトルネックの特定から改善までどう進めますか
まず計測から始めます。推測で動かず、APMツールやプロファイラで定量的なデータを取得し、遅延箇所を特定します。
次に、データに基づき仮説を立てます(例:「このクエリのJOINが原因ではないか」)。そして、仮説に基づいた改善策を一つずつ実施し、その都度効果測定を行います。
一度に複数変更すると原因が分からなくなるためです。最後に、改善後は再発防止のため、関連メトリクスの継続的な監視を設定します。
● スケーラビリティを考慮した設計のポイントは何ですか
重要なポイントは2つあります。1つ目はステートレスなアーキテクチャです。サーバーが状態を持たなければ、単純にサーバーの数を増やす水平スケールが容易になります。セッション情報などは、Redisなどの外部ストアに保持します。
2つ目はコンポーネントの疎結合化です。機能を独立したサービスに分割し、APIやメッセージキューで非同期に連携させることで、特定のサービスだけを独立してスケールさせることができ、システム全体の柔軟性が高まります。
● 大規模システムの設計から実装まで主導した経験はありますか
前職で月間数億リクエストを処理する広告配信システムの再設計プロジェクトを技術リーダーとして主導しました。
モノリシック構成による開発効率とスケーラビリティの課題を解決するため、マイクロサービスアーキテクチャの採用を提案・設計しました。
技術選定からアーキテクチャ設計、チームへのタスク分割、他部署との調整までを一貫して担当し、リリースサイクルの50%向上とインフラコストの20%削減を実現しました。
● マイクロサービスアーキテクチャの設計経験について聞かせてください
広告配信システムの再設計で経験しました。
設計では、ドメイン駆動設計(DDD)のアプローチでサービスの分割境界を決定し、サービス間のデータ一貫性を保つためにSagaパターンを導入しました。
また、各サービスがブラックボックス化しないよう、分散トレーシングや構造化ロギングといったオブザーバビリティの確保を重視しました。
サービス間通信は同期処理にgRPC、非同期処理にKafkaを採用し、インフラはKubernetes上で運用しました。
● CI/CDパイプラインの構築・運用経験はありますか
JenkinsとGitLab CIを用いて、コードプッシュから本番リリースまでを自動化するパイプラインを構築・運用しました。
CIでは、プッシュをトリガーにビルド、単体テスト、静的コード解析を実行し、品質を担保しました。
CDでは、ステージング環境への自動デプロイに加え、本番環境へはCanaryリリースを導入し、安全なリリースを実現しました。
パイプラインの実行時間を監視し、テストの並列化などで継続的に改善も行っていました。
● 技術的な意思決定はどのようなプロセスで行いますか
まず、解決すべき課題と目的を明確にします。次に、複数の技術候補をリストアップし、それぞれのメリット・デメリット、学習コスト、将来性などをまとめた比較ドキュメントを作成します。
そのドキュメントを基にチーム内で議論し、技術的な観点だけでなく、ビジネス的な観点も含めて検討します。
必要であれば小規模なPoC(概念実証)を行い、最終的な判断を下します。決定後は、その理由と経緯をドキュメントとして残し、チーム全体で共有するようにしています。
● チームメンバーのスキルアップ支援はどう行っていますか
主に3つの方法で支援しています。
1つ目はペアプログラミングやモブプログラミングの積極的な実施です。これにより、実践的なスキルや設計思想を直接伝えることができます。
2つ目は定期的な1on1です。メンバーのキャリア志向や興味を聞き、それに合ったタスクをアサインしたり、学習リソースを推薦したりします。
3つ目は知識共有会の開催です。新しい技術の調査結果や、プロジェクトで得た知見を発表する場を設け、チーム全体の技術力向上を図っています。
● 新技術導入時のリスク評価はどう行いますか
まず、技術的リスクとして、その技術の成熟度、コミュニティの活発さ、将来性を評価します。
バグが多い、ドキュメントが少ないといったリスクがないかを確認します。次に、人的リスクとして、チームの学習コストや、市場でのその技術を持つエンジニアの採用難易度を考慮します。
最後に、運用的リスクとして、導入後の保守コストや、既存システムとの連携問題を評価します。これらのリスクを総合的に判断し、導入可否や、影響範囲を限定したスモールスタートが可能かなどを検討します。
4-2. フロントエンドエンジニアの怒涛の技術質問18選
フロントエンドエンジニアが聞かれる技術質問は以下の通りです。
- JavaScriptのイベントループについて説明できますか
- Promiseとasync/awaitはどう使い分けていますか
- DOMと仮想DOMの違いは何ですか
- Reactのライフサイクルメソッドについて教えてください
- Vue.jsのリアクティブシステムはどういう仕組みですか
- SPAとMPAはどう使い分けますか
- Webページの表示速度改善で何をしていますか
- バンドルサイズの最適化はどうやっていますか
- メモリリークが起きる原因と対策は何ですか
- TypeScript導入のメリットは何だと思いますか
- CSS-in-JSとCSS Modulesはどう使い分けますか
- PWA実装で苦労した点はありますか
- 大規模なフロントエンドアプリケーションの設計経験はありますか
- マイクロフロントエンドの実装経験はありますか
- 状態管理ライブラリはどう選んでいますか
- フロントエンドの技術選定はどう進めますか
- デザインシステムの構築経験はありますか
- アクセシビリティの実装指導はどうしていますか
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
● JavaScriptのイベントループについて説明できますか
JavaScriptはシングルスレッドですが、イベントループの仕組みによって非同期処理を実現しています。
まず、実行コードはコールスタックに積まれます。setTimeoutのような非同期APIが呼ばれると、処理はWeb APIに移り、コールバック関数は完了後にタスクキューに入ります。
イベントループは、コールスタックが空になるのを監視し、空になったらタスクキューからコールバック関数をスタックに積んで実行します。これにより、重い処理を待たずに次の処理に進め、UIのブロッキングを防いでいます。
● Promiseとasync/awaitはどう使い分けていますか
async/awaitはPromiseをより直感的に書けるようにしたシンタックスシュガーなので、基本的には可読性の高いasync/awaitを優先して使います。
非同期処理を上から順に、同期処理のように記述できるのが利点です。
ただし、複数の非同期処理を並行して実行し、すべて完了してから次の処理に進みたい場合はPromise.allを使います。また、複雑なエラーハンドリングをメソッドチェーンで記述したい場合も、Promiseの.then()や.catch()を直接使うことがあります。
● DOMと仮想DOMの違いは何ですか
DOMはブラウザがHTMLを解釈して作るツリー構造のオブジェクトで、これを直接操作すると再描画のコストが高くなります。
一方、仮想DOMは、DOMを模した軽量なJavaScriptオブジェクトです。
Reactなどでは、状態が変更されると、まず新しい仮想DOMツリーを作り、前回のツリーとの差分を計算します。そして、その差分だけを実際のDOMにまとめて一度に適用します。
これにより、不要なDOM操作を最小限に抑え、パフォーマンスを向上させることができます。
● Reactのライフサイクルメソッドについて教えてください
Reactのコンポーネントが生成されてから破棄されるまでの一連の流れの中で、特定のタイミングで呼ばれるメソッドです。
主に、コンポーネントがDOMに挿入されるマウンティング期(componentDidMountなど)、propsやstateの変更で再描画される更新期(componentDidUpdateなど)、DOMから削除されるアンマウンティング期(componentWillUnmount)の3つに分かれます。
関数コンポーネントでは、これらのライフサイクルは主にuseEffectフックで実現します。
● Vue.jsのリアクティブシステムはどういう仕組みですか
データが変更されると、UIが自動的に更新される仕組みです。
Vue 3ではJavaScriptのProxyを用いて実現されています。コンポーネントのdataオブジェクトがProxyでラップされ、プロパティへのアクセス(get)や変更(set)が検知されます。
テンプレート内でデータが使われると、どのUIがそのデータに依存しているかが記録されます。データが変更されると、依存関係のあるUIに更新が通知され、再描画が起こります。
● SPAとMPAはどう使い分けますか
SPA(Single Page Application)は、単一のページでコンテンツを動的に書き換えるため、ページ遷移が高速でネイティブアプリのような体験を提供できます。Gmailのようなインタラクティブ性の高いWebアプリケーションに適しています。
一方、MPA(Multiple Page Application)は、ページ遷移ごとにサーバーから新しいHTMLを取得する伝統的な方式です。各ページが独立しているためSEOに強く、ブログやコーポレートサイトのような静的コンテンツ中心のサイトに適しています。
● Webページの表示速度改善で何をしていますか
Lighthouseなどのツールでパフォーマンスを計測し、Core Web Vitalsの指標を基に改善します。
具体的には、レンダリングをブロックするリソースの削減、画像の遅延読み込み(Lazy Loading)や次世代フォーマット(WebP)での配信、CDNを活用した静的アセットの配信、不要なJavaScriptの削除などを行います。
また、サーバーサイドレンダリング(SSR)や静的サイト生成(SSG)を導入し、FCPやLCPを改善することも検討します。
● バンドルサイズの最適化はどうやっていますか
Webpack Bundle Analyzerなどのツールを使って、バンドルファイルの内容を可視化し、不要にサイズが大きくなっているライブラリがないかを確認します。
その上で、Tree Shakingを有効にして未使用のコードを削除したり、Code Splittingを導入してルートごとに必要なコードだけを読み込むように分割したりします。
また、moment.jsのようにサイズの大きいライブラリは、Day.jsなどの軽量な代替ライブラリに置き換えることも検討します。
● メモリリークが起きる原因と対策は何ですか
メモリリークは、不要になったメモリが解放されずに残り続けることで発生します。
フロントエンドでは、グローバル変数への意図しない参照、削除したDOM要素への参照が残っている、addEventListenerで登録したイベントリスナーをremoveEventListenerで解除し忘れる、といったことが主な原因です。
対策としては、ChromeのDevToolsなどを使ってメモリのスナップショットを比較し、解放されていないオブジェクトを特定します。
そして、不要になった参照を明示的にnullでクリアしたり、コンポーネントのクリーンアップ処理でイベントリスナーを確実に解除したりします。
● TypeScript導入のメリットは何だと思いますか
最大のメリットは静的型付けによる安全性の向上です。コンパイル時に型エラーを検出できるため、実行時エラーを大幅に減らせます。
また、エディタの補完機能が強力に働くため、開発効率が向上し、コードの可読性も高まります。
特に大規模なアプリケーションやチーム開発では、型がドキュメントの役割も果たし、コンポーネントのインターフェースが明確になるため、保守性が格段に向上すると考えています。
● CSS-in-JSとCSS Modulesはどう使い分けますか
コンポーネントの動的なスタイリング要件によって使い分けます。
propsに応じてスタイルを頻繁に変更するなど、JavaScriptの状態と密接に連携するスタイルが必要な場合は、styled-componentsなどのCSS-in-JSが適しています。
一方、コンポーネントごとにスコープが閉じられた静的なスタイルを適用したいだけであれば、CSS Modulesがシンプルで学習コストも低く、ビルド時に純粋なCSSファイルを生成するためパフォーマンス面でも有利です。
● PWA実装で苦労した点はありますか
Service Workerのキャッシュ戦略の実装で苦労しました。
特に、キャッシュの更新タイミングの制御が難しく、古いコンテンツが表示され続けてしまう問題や、逆に更新が頻繁すぎてパフォーマンスが劣化する問題に直面しました。
これを解決するため、stale-while-revalidate(キャッシュを返しつつ裏で更新)やnetwork-first(ネットワークを優先し失敗時にキャッシュ)といった戦略を、コンテンツの特性に応じて使い分けることの重要性を学びました。
● 大規模なフロントエンドアプリケーションの設計経験はありますか
コンポーネントをAtomic Designの考え方に基づいて分割し、再利用性と見通しを良くしました。
また、状態管理が複雑化しないよう、グローバルな状態はZustandやRecoilのようなライブラリで管理し、コンポーネントローカルな状態と明確に分離しました。
ルーティングや認証、データ取得といった関心事は、それぞれ専用のレイヤーに分割し、責務が混在しないクリーンなアーキテクチャを目指しました。
● マイクロフロントエンドの実装経験はありますか
大規模なポータルサイトの開発で、Module Federationを用いてマイクロフロントエンドを実装した経験があります。
各チームが担当する機能を独立したアプリケーションとして開発・デプロイし、それらをコンテナとなるアプリケーションが実行時に動的に読み込む構成にしました。
これにより、チーム間の開発サイクルの独立性が保たれ、技術スタックの自由度も高まりました。一方で、共通UIコンポーネントのバージョン管理や、アプリケーション全体での状態共有の設計には課題があり、チーム間の密な連携が必要でした。
● 状態管理ライブラリはどう選んでいますか
アプリケーションの規模と状態の複雑性に基づいて選びます。
小規模なアプリケーションや、状態のほとんどがサーバーサイドにある場合は、React QueryやSWRのようなデータフェッチングライブラリで十分なことが多いです。
クライアント側で複雑なグローバル状態を持つ必要がある場合は、Redux ToolkitやZustand、Recoilなどを候補とします。
選定基準は、学習コスト、ボイラープレートの量、コミュニティの活発さ、そして非同期処理やミドルウェアとの連携のしやすさなどを総合的に評価します。
● フロントエンドの技術選定はどう進めますか
まず、プロジェクトの要件(パフォーマンス、SEO、インタラクティビティ等)を明確にします。
次に、要件を満たす複数のフレームワークやライブラリを候補として挙げ、それぞれのアーキテクチャ、エコシステム、学習コスト、将来性を比較したドキュメントを作成します。
その上で、チームメンバーと議論し、必要であれば小規模なPoCを実施して技術的な実現可能性や開発体験を評価します。
最終的には、短期的な開発効率だけでなく、長期的な保守性やチームの成長といった観点も踏まえて意思決定します。
● デザインシステムの構築経験はありますか
UIコンポーネント(ボタン、フォームなど)をReactコンポーネントとして実装し、Storybookを用いてカタログ化しました。
デザイントークン(色、フォントサイズ、スペースなど)をJSON形式で一元管理し、CSS in JSを通じて各コンポーネントに適用する仕組みを構築しました。
これにより、デザインの一貫性が保たれ、デザイナーとエンジニア間のコミュニケーションも円滑になりました。また、Figmaで作成されたデザインとコンポーネントの連携も意識して設計しました。
● アクセシビリティの実装指導はどうしていますか
まず、WCAGのガイドラインを基にした実装チェックリストを作成し、チームで共有します。
コードレビューでは、セマンティックなHTMLタグの使用、画像に対する適切なalt属性、キーボードのみでの操作が可能か、十分なコントラスト比が確保されているか、といった点を重点的に確認します。
また、axeなどの自動チェックツールをCIに組み込むことを推奨し、定期的にスクリーンリーダーを使った手動テストを実施して、実践的なアクセシビリティ向上をチーム全体で推進します。
4-3.バックエンドエンジニアの怒涛の技術質問18選
バックエンドエンジニアの技術質問で聞かれるのは以下の通りです。
- RESTful APIの設計で何を意識していますか
- HTTPステータスコードはどう使い分けていますか
- JWTとOAuthの違いは何ですか
- SQLのパフォーマンス改善で何をしていますか
- トランザクションはどんな時に使いますか
- RDBMSとNoSQLはどう使い分けますか
- APIのバージョン管理はどうしていますか
- 非同期処理の実装で何を使っていますか
- キャッシュ戦略はどう設計していますか
- データベースの負荷分散経験はありますか
- アプリケーションのスケーリング経験はありますか
- 監視とログはどう設計していますか
- マイクロサービスの設計・運用経験はありますか
- イベントドリブンアーキテクチャの実装経験はありますか
- 分散システムで苦労した点はありますか
- 技術的負債の解消はどう進めていますか
- セキュリティを考慮した設計で何を重視しますか
- 開発チームの生産性向上で何をしていますか
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
● RESTful APIの設計で何を意識していますか
リソース中心の設計を意識しています。URIは名詞の複数形(例:/users)でリソースを表現し、そのリソースに対する操作はHTTPメソッド(GET, POST, PUT, DELETE)で表現するようにします。
また、レスポンスのフォーマットはJSONで統一し、成功・失敗が明確にわかるように適切なHTTPステータスコードを返すことを心がけています。これにより、直感的で分かりやすいAPIを目指しています。
● HTTPステータスコードはどう使い分けていますか
リクエストの結果を正確に伝えるために使い分けます。
成功時は200 OK、リソース作成成功時は201 Created、削除成功時は204 No Contentを返します。
クライアント側のエラーでは、バリデーションエラーなどに400 Bad Request、認証失敗に401 Unauthorized、権限不足に403 Forbidden、リソース不在に404 Not Foundを使います。
サーバー側の問題では、予期せぬエラーに500 Internal Server Errorを返します。
● JWTとOAuthの違いは何ですか
JWT(JSON Web Token)は、認証情報を表現するためのトークンの「仕様」です。ユーザー情報などをJSON形式で含み、署名によって改ざんを検知できます。
一方、OAuth 2.0は、認可のための「フレームワーク」または「プロトコル」です。ユーザーの同意のもと、あるサービスが別のサービスのリソースにアクセスする権限を安全に委譲する仕組みです。
OAuthのフローの中で、認証情報を示すアクセストークンとしてJWTが使われることはよくあります。
● SQLのパフォーマンス改善で何をしていますか
まず、EXPLAINを使ってクエリの実行計画を確認します。WHERE句やJOIN句で使われるカラムにインデックスが適切に貼られているかを確認し、なければ追加します。
また、SELECT *のように不要なカラムまで取得せず、必要なカラムだけを明示的に指定するようにします。サブクエリを多用している場合は、JOINで書き換えられないか検討することもあります。
● トランザクションはどんな時に使いますか
複数のデータベース操作を、すべて成功するかすべて失敗するかのどちらかに保証したい、つまり原子性を保ちたい時に使います。
例えば、銀行の振込処理です。「Aさんの口座から引き落とす」という操作と、「Bさんの口座に入金する」という操作は、両方成功しなければなりません。
片方だけ成功してデータに不整合が起きるのを防ぐために、一連の処理を一つのトランザクションとしてまとめます。
● RDBMSとNoSQLはどう使い分けますか
データの構造と一貫性の要件によって使い分けます。RDBMS(MySQL, PostgreSQLなど)は、厳密なスキーマとトランザクションによる強い一貫性が求められるデータ、例えば金融システムや基幹業務システムに適しています。
一方、NoSQLは、スキーマレスで柔軟なデータ構造を持ち、大量のデータの書き込みや水平スケーリングが求められる場面、例えばSNSの投稿データやIoTデバイスのログデータなどに適しています。
● APIのバージョン管理はどうしていますか
クライアントへの影響を最小限に抑えるため、URIにバージョン情報を含めるパスベースのバージョニング(例:/v1/users)を採用することが多いです。
破壊的な変更を加える際は、新しいバージョンのエンドポイント(/v2/users)を用意し、古いバージョンも一定期間併存させます。これにより、クライアントは自身のタイミングで新しいバージョンに移行できます。
移行期間や廃止時期については、APIドキュメントやカスタムヘッダーで事前に告知するようにしています。
● 非同期処理の実装で何を使っていますか
用途に応じて使い分けます。比較的シンプルなタスクや、即時性がそれほど求められない処理(例:メール送信、画像のリサイズ)には、RedisやRabbitMQのようなメッセージキューイングシステムを利用します。
リクエストをキューに積んで、別のワーカプロセスで非同期に処理させます。
大量のデータをリアルタイムでストリーム処理する必要がある場合(例:ログ収集、イベント分析)には、Kafkaのような分散ストリーミングプラットフォームの採用を検討します。
● キャッシュ戦略はどう設計していますか
まず、キャッシュ対象のデータの特性(更新頻度、許容できる古さ)を分析します。
更新頻度が低く、多くのユーザーで共通して利用できるデータは、CDNやリバースプロキシでのキャッシュを検討します。
ユーザーごとに異なるデータや、より頻繁に更新されるデータは、RedisやMemcachedのような分散キャッシュサーバーをアプリケーションの近くに配置します。
キャッシュの無効化(パージ)戦略としては、データの更新時に明示的にキャッシュを削除する方法や、短いTTL(Time To Live)を設定する方法を使い分けます。
● データベースの負荷分散経験はありますか
参照系の負荷を分散させるため、リードレプリカを導入した経験があります。書き込みはプライマリDBで行い、その更新がレプリケーションによって複数のリードレプリカに同期されます。
アプリケーション側では、書き込み系のクエリはプライマリDBへ、参照系のクエリはリードレプリカへ振り分けるように実装しました。
これにより、プライマリDBの負荷を大幅に軽減し、システム全体の読み取り性能を向上させることができました。
● アプリケーションのスケーリング経験はありますか
ステートレスなWebアプリケーションの水平スケーリング(スケールアウト)を経験しました。
ユーザーのセッション情報をサーバー内ではなく、Redisなどの外部の共有データストアに保存するようにアプリケーションを改修しました。
これにより、どのサーバーがリクエストを受け取っても処理を継続できるようになり、ロードバランサー配下のサーバーインスタンスを単純に増減させるだけで、トラフィックの増減に柔軟に対応できる構成を実現しました。
● 監視とログはどう設計していますか
監視は、アプリケーションの健全性を多角的に把握できるよう設計します。
CPU使用率やメモリ使用量といったリソース監視に加え、レスポンスタイムやエラーレートといったアプリケーションのパフォーマンスメトリクス(APM)を重視します。
ログは、単なるテキストではなく、リクエストIDやユーザーIDといった情報を含む構造化ログ(JSON形式など)として出力します。
これにより、Fluentdなどでログを一元的に収集し、Elasticsearchなどで横断的に検索・分析することが容易になり、障害調査の迅速化に繋がります。
● マイクロサービスの設計・運用経験はありますか
モノリシックだったECサイトをマイクロサービスアーキテクチャに移行するプロジェクトを主導しました。ドメイン駆動設計に基づき、商品、在庫、注文、決済といった単位でサービスを分割しました。
サービス間通信は、同期処理にはgRPCを、非同期処理にはメッセージキュー(RabbitMQ)を採用しました。
運用では、各サービスをKubernetes上で独立してデプロイ・スケールできるようにし、オブザーバビリティ確保のために分散トレーシングや集中ログ基盤を導入しました。
● イベントドリブンアーキテクチャの実装経験はありますか
注文処理システムで実装経験があります。「注文作成」というイベントが発生すると、そのイベントをメッセージブローカー(Kafka)に発行します。
在庫サービス、決済サービス、配送サービスといった関連するマイクロサービスがそのイベントを購読(サブスクライブ)し、それぞれが独立して在庫の引き当てや決済処理、配送手配といった自身の責務を非同期に実行します。
これにより、サービス間の結合度が下がり、柔軟で回復力の高いシステムを実現しました。
● 分散システムで苦労した点はありますか
データの一貫性の担保に最も苦労しました。特に、複数のマイクロサービスにまたがる処理で、一部のサービスが失敗した場合に全体の整合性をどう保つかという課題がありました。
これを解決するため、分散トランザクションではなく、結果整合性を許容するSagaパターンを導入しました。
各サービスがローカルトランザクションを実行し、途中で失敗した場合は、それまでの処理を取り消すための補償トランザクションを実行する、という実装は複雑で、デバッグにも時間がかかりました。
● 技術的負債の解消はどう進めていますか
まず、技術的負債を可視化し、ビジネスへの影響度(機会損失、障害リスクなど)と、解消にかかる工数を評価して優先順位を付けます。
そして、すべての開発を止めて返済に集中するのではなく、通常の機能開発のスプリントの中に、一定の割合(例えば20%)で負債解消のためのタスクを組み込むようにします。
また、新しい負債を生まないために、コードレビューの基準を厳格化したり、リファクタリングを推奨する文化をチームに根付かせたりすることも同時に進めます。
● セキュリティを考慮した設計で何を重視しますか
「多層防御(Defense in Depth)」の考え方を重視します。単一のセキュリティ対策に頼るのではなく、ネットワーク層、インフラ層、アプリケーション層など、複数のレイヤーで対策を講じます。
具体的には、脆弱性のあるライブラリを使わない(依存関係のスキャン)、SQLインジェクションやXSSといった一般的な脆弱性への対策をフレームワークレベルで徹底する、最小権限の原則に基づきアクセス制御を厳格に行う、そして全ての通信を暗号化するといった基本的な対策を漏れなく実施することを重視しています。
● 開発チームの生産性向上で何をしていますか
開発プロセスにおける無駄や手戻りをなくすことに注力しています。
具体的には、CI/CDパイプラインを整備してテストやデプロイを自動化し、開発者が本来の価値創造に集中できる環境を整えます。
また、開発に必要な環境をコード化(Infrastructure as Code)し、誰でもすぐに開発を始められるようにします。
プロセス面では、定期的なふりかえり(レトロスペクティブ)を通じてチームの課題を特定し、継続的な改善サイクルを回すことを推進しています。
4-4.組み込みエンジニアの怒涛の技術質問18選
組み込みエンジニアの技術質問は以下の通りです。
- ポインタと参照の使い分けについて教えてください
- メモリ管理で注意していることはありますか
- 構造体とクラスの使い分けはどうしていますか
- 組み込み開発の流れについて教えてください
- マイコンとマイクロプロセッサの違いは何ですか
- 割り込み処理の実装で気をつけることはありますか
- RTOSの使用経験はありますか
- タスクスケジューリングはどう設計していますか
- デッドロック対策で何をしていますか
- 組み込みシステムのデバッグはどうしていますか
- メモリ制約下での最適化経験はありますか
- 電力消費を考慮した実装経験はありますか
- 組み込みシステムの全体設計を主導した経験はありますか
- 通信プロトコルの設計・実装経験はありますか
- セキュリティを考慮した組み込み開発経験はありますか
- チームの技術指導はどうしていますか
- 開発プロセスの改善経験はありますか
- 品質保証の取り組みについて教えてください
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
● ポインタと参照の使い分けについて教えてください
ポインタと参照はどちらも間接的にオブジェクトを扱いますが、性質が異なります。
ポインタは、指し示すアドレスを自由に変更でき、何も指さない状態(NULL)も表現できます。そのため、指し示す先が可変である場合や、オブジェクトが存在しない可能性がある場合に使います。
一方、参照は一度初期化すると別のオブジェクトを指すようには変更できず、必ず何らかのオブジェクトを指します。
そのため、指し示す対象が不変で、かつNULLでないことが保証されている場面で、より安全なコードとして参照を使います
● メモリ管理で注意していることはありますか
動的に確保したメモリの解放漏れ(メモリリーク)と、解放済みのメモリへのアクセス(二重解放など)に最も注意しています。
mallocやnewで確保したメモリは、必ず対応するfreeやdeleteで解放することを徹底します。特に、関数の途中でエラーリターンする場合の解放漏れには注意が必要です。
また、メモリ確保の失敗(NULLが返る)を必ずチェックし、NULLポインタへのアクセスを防ぐようにしています。
● 構造体とクラスの使い分けはどうしていますか
C++においては、アクセス指定子のデフォルトが異なる(構造体はpublic、クラスはprivate)という違いがありますが、本質的にはデータの集合体としてシンプルに扱いたい場合は構造体を使います。
例えば、座標データ(x, y, z)のように、データを保持することが主目的で、複雑な振る舞い(メソッド)を持たない場合です。
一方、データとそのデータを操作する振る舞いをカプセル化し、隠蔽したい情報がある場合や、継承などを使いたい場合はクラスを使います。
● 組み込み開発の流れについて教えてください
まず、要求仕様に基づき、どのようなハードウェア(マイコン、センサー等)が必要かを決定し、システム全体の設計を行います。次に、そのハードウェア上で動作するソフトウェアの設計を行い、C/C++などの言語でプログラミングします。
書いたコードは、PC上でクロスコンパイラを使ってターゲットのマイコンが理解できる機械語に変換(ビルド)します。
生成されたバイナリファイルを、デバッガ(JTAGなど)を使ってマイコンに書き込み、実機で動作確認とデバッグを繰り返して完成させます。
● マイコンとマイクロプロセッサの違いは何ですか
マイクロプロセッサ(MPU)は、演算処理を行うCPU機能に特化した集積回路です。PCのように、メモリや周辺機能は外付けで接続してシステムを構築します。
一方、マイコン(MCU)は、CPUコアに加え、プログラムを格納するROM(フラッシュメモリ)、データを一時的に保持するRAM、タイマーやA/Dコンバータといった周辺機能を一つのチップにまとめたものです。
そのため、マイコン単体で小規模なシステムを制御でき、家電製品などの組み込みシステムで広く使われます。
● 割り込み処理の実装で気をつけることはありますか
割り込み処理(ISR)は、できるだけ短く、高速に完了させることを最も意識します。
ISRの実行中は、他の割り込みがブロックされたり、メインの処理が停止したりするため、長時間占有するとシステム全体のリアルタイム性を損なうからです。
ISR内では、重い処理は行わず、フラグを立てるなどの最小限の処理に留め、実際の処理はメインループ側で行うようにします。
また、ISR内で使用する変数は、volatileキーワードを付けて、コンパイラの最適化によって意図しない動作になることを防ぎます。
● RTOSの使用経験はありますか
はい、FreeRTOSを使用した経験があります。複数のセンサーからのデータを並行して処理し、ネットワーク通信を行うシステム開発で利用しました。
各機能を独立したタスクとして実装し、タスク間の同期や通信にはセマフォやキューを使用しました。
RTOSを導入したことで、複雑な処理のスケジューリングをOSに任せることができ、ソフトウェアの構造がシンプルになり、見通しが良くなりました。
● タスクスケジューリングはどう設計していますか
まず、システムの要求するリアルタイム性に基づいて、各タスクの優先度を決定します。
締め切り時間が厳密な処理(例:モーター制御)には高い優先度を、比較的緩やかな処理(例:UI表示)には低い優先度を割り当てます。プリエンプティブなスケジューリングを基本とし、優先度の高いタスクが即座に実行されるようにします。
また、優先度の低いタスクが実行機会を失わないよう(スタベーション)、必要に応じて優先度逆転を防ぐ仕組み(優先度継承など)の導入も検討します。
● デッドロック対策で何をしていますか
デッドロックの発生条件である「相互排除」「保持と待機」「非プリエンプション」「循環待ち」のいずれかを崩すように設計します。
最も実践的なのは「循環待ち」の条件を崩すことで、複数の共有リソース(セマフォなど)を獲得する際に、必ず決められた順序で獲得するようにコーディングルールを徹底します。
これにより、タスク間でお互いのリソースを待ち続ける循環状態を防ぎます。また、そもそもロックの粒度を小さくしたり、ロックフリーな実装が可能か検討したりすることも重要です。
● 組み込みシステムのデバッグはどうしていますか
JTAGやSWDといったハードウェアデバッガを主に使います。ブレークポイントを設定して任意の場所でプログラムを停止させ、その時点での変数の値やメモリ、レジスタの状態を確認します。
リアルタイム性が重要でプログラムを止められない場合は、printfデバッグのようにUART経由でログを出力したり、ロジックアナライザを使ってGPIOの波形を観測し、処理のタイミングや状態を外部から確認したりします。
● メモリ制約下での最適化経験はありますか
はい、あります。RAMが数KBしかないマイコンで、スタックオーバーフローが頻発する問題に対応しました。まず、各関数のローカル変数が過大でないかを見直し、不要な変数を削減しました。
また、大きなデータ構造は静的領域に配置するか、必要になるまで動的確保しないように変更しました。
コードサイズ(ROM)の削減では、コンパイラの最適化オプションを調整したり、使用頻度の低いライブラリ関数をより軽量な自作関数に置き換えたりするなどの工夫を行いました。
● 電力消費を考慮した実装経験はありますか
バッテリー駆動のIoTデバイス開発で、低消費電力化に取り組みました。
処理を行っていない待機時間には、マイコンをスリープモードやディープスリープモードに移行させ、消費電流を極力抑えるように実装しました。
タイマー割り込みや外部ピンの割り込みをトリガーに必要な処理が完了したら即座にスリープに戻る、というサイクルを繰り返します。また、CPUの動作クロック周波数を、必要最低限の速度に動的に変更することでも消費電力を削減しました。
● 組み込みシステムの全体設計を主導した経験はありますか
FA機器の制御システムの開発プロジェクトで、ソフトウェア全体のアーキテクチャ設計を主導しました。
ハードウェアチームと連携して要求仕様を分析し、使用するマイコンやOS(RTOS)を選定しました。ソフトウェアの機能ブロックを定義し、各ブロック間のインターフェース(API)を設計しました。
また、タスク分割やスケジューリング方針、メモリマップ、エラーハンドリングの共通ルールなどを策定し、チームメンバーが統一された設計思想のもとで開発を進められるようドキュメント化と共有を徹底しました。
● 通信プロトコルの設計・実装経験はありますか
独自のシリアル通信プロトコルを設計・実装した経験があります。複数のセンサーノードとマスターコントローラー間でデータをやり取りするためのプロトコルで、ヘッダー、データ長、ペイロード、チェックサムからなるパケットフォーマットを定義しました。
通信エラーを考慮し、再送要求やACK/NACKの仕組みを取り入れ、信頼性を確保しました。
また、状態遷移図を用いてプロトコルのシーケンスを厳密に定義し、実装時の曖昧さを排除しました。
● セキュリティを考慮した組み込み開発経験はありますか
ネットワーク接続機能を持つコンシューマ向けIoT機器の開発で、セキュリティ設計を担当しました。主な対策として、セキュアブートを導入して不正なファームウェアの起動を防止しました。
また、通信経路はTLSで暗号化し、ファームウェアのアップデート時には電子署名による検証を行う仕組みを実装しました。
さらに、デバッグ用のポート(JTAG, UART)を製品版では無効化し、物理的な攻撃に対する耐性も高めました。
● チームの技術指導はどうしていますか
コードレビューを重要な指導の機会と捉えています。単に問題点を指摘するだけでなく、「なぜこう書く方が良いのか」という設計思想や背景まで伝えるようにしています。
また、定期的に勉強会を開催し、新しい技術要素や、過去のプロジェクトで発生したバグの原因と対策などを共有し、チーム全体の知識の底上げを図っています。
若手メンバーには、少し挑戦的なタスクを任せ、1on1で進捗のフォローや技術的な相談に乗ることで、自律的な成長をサポートしています。
● 開発プロセスの改善経験はありますか
従来のウォーターフォール型開発で手戻りが多かったプロセスに対し、CI(継続的インテグレーション)の導入を提案・推進しました。
Gitでのバージョン管理を徹底し、Jenkinsサーバーを構築して、コードのプッシュをトリガーに自動ビルドと静的解析、単体テストが実行される環境を整えました。
これにより、バグを早期に発見できるようになり、結合テストフェーズでの手戻りが大幅に削減され、開発効率が向上しました。
● 品質保証の取り組みについて教えてください
開発の初期段階から品質を意識することを重視しています。
まず、設計段階でレビューを徹底し、仕様の矛盾や考慮漏れをなくします。実装では、静的解析ツールや単体テストをCIに組み込み、コードレベルでの品質を担保します。
そして、実機での結合テストやシステムテストでは、正常系だけでなく、想定される異常系や境界値のテストケースを網羅的に作成し、実施します。
これらのテストは可能な限り自動化し、回帰テストを効率的に行えるようにしています。
5.インフラエンジニア職種の怒涛の技術質問90選
インフラエンジニアの5職種の技術質問を掲載しています。
- ネットワークエンジニアの技術質問18選
- サーバーエンジニアの技術質問18選
- クラウドエンジニアの技術質問18選
- セキュリティエンジニアの技術質問18選
- データベースエンジニアの技術質問18選
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
5-1.ネットワークエンジニアの怒涛の技術質問18選
ネットワークエンジニアの技術質問は以下の通りです。
- OSI 7層モデルの各層の役割について説明してください
- TCPとUDPの違いと使い分けは何ですか
- サブネットマスクの計算はできますか
- VLANの設定経験はありますか
- ルーティングテーブルの確認方法を教えてください
- ファイアウォールの設定経験はありますか
- ネットワークのボトルネック特定はどうしていますか
- 冗長化設計の実装経験はありますか
- 監視システムの構築経験はありますか
- ネットワークセキュリティの脅威と対策について教えてください
- パフォーマンス低下時の調査手順はどうしていますか
- 障害対応の優先順位はどう決めていますか
- 企業ネットワークの全体設計経験はありますか
- クラウドとオンプレのハイブリッド構成経験はありますか
- SDNの導入検討・実装経験はありますか
- ネットワーク技術選定の判断基準は何ですか
- 運用自動化の推進経験はありますか
- チームメンバーの技術指導はどうしていますか
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
● OSI 7層モデルの各層の役割について説明してください
OSI参照モデルは、通信機能を7つの階層に分けて定義したものです。
下から、物理的な接続を定める第1層物理層、隣接ノード間の通信を担う第2層データリンク層、ネットワーク間の通信経路を決定する第3層ネットワーク層、通信の信頼性を確保する第4層トランスポート層、通信の開始から終了までを管理する第5層セッション層、データの表現形式を統一する第6層プレゼンテーション層、そしてアプリケーション固有の通信サービスを提供する第7層アプリケーション層で構成されます。
● TCPとUDPの違いと使い分けは何ですか
TCPとUDPはどちらもトランスポート層のプロトコルですが、信頼性の扱いが異なります。TCPは、3ウェイハンドシェイクでコネクションを確立し、順序制御や再送制御を行うため、信頼性の高い通信が可能です。
一方、UDPはコネクションを確立せず、データを送りっぱなしにするため、高速ですが信頼性は保証されません。
そのため、Webやメールのようにデータの完全性が重要な通信にはTCPを、DNSや動画ストリーミング、オンラインゲームのように、多少のデータ欠損よりも速度やリアルタイム性が重視される通信にはUDPを使い分けます。
● サブネットマスクの計算はできますか
サブネットマスクは、IPアドレスのどこまでがネットワーク部で、どこからがホスト部かを示すために使われます。
例えば、IPアドレス 192.168.1.100 にサブネットマスク 255.255.255.0(または /24)を適用すると、上位24ビットがネットワーク部、下位8ビットがホスト部となります。
これにより、ネットワークアドレスは 192.168.1.0 となり、このネットワークには2の8乗マイナス2、つまり254台のホストが所属できることがわかります。
● VLANの設定経験はありますか
物理的な接続構成を変更せずに、スイッチの設定によって仮想的なLANセグメントを構築するためにVLANを使用しました。
例えば、部署ごとにブロードキャストドメインを分割するために、特定のスイッチポートを特定のVLAN IDに割り当てる「ポートベースVLAN」を設定した経験があります。
これにより、不要なトラフィックの削減と、セキュリティの向上を実現しました。
● ルーティングテーブルの確認方法を教えてください
Windowsではroute printまたはnetstat -rコマンド、LinuxやCiscoルータではip routeまたはshow ip routeコマンドで確認します。
ルーティングテーブルには、宛先ネットワーク、ネクストホップ(次にパケットを送るべきルータのアドレス)、使用するインターフェースなどの情報が記載されています。
これにより、特定の宛先へのパケットが、どの経路を通って転送されるかを確認できます。
● ファイアウォールの設定経験はありますか
特定の送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、プロトコル(TCP/UDP)、ポート番号の組み合わせに基づいて、通信を許可または拒否するアクセスコントロールリスト(ACL)を設定した経験があります。
例えば、外部から社内サーバーへのアクセスについて、Webアクセス用のTCP/80番ポートとTCP/443番ポートのみを許可し、それ以外の通信はすべて拒否する、といった基本的なセキュリティポリシーを実装しました。
● ネットワークのボトルネック特定はどうしていますか
まず、SNMPやNetFlowなどのプロトコルを用いて、ネットワーク機器のトラフィック量、CPU使用率、エラーパケット数などを継続的に監視します。
パフォーマンスの劣化が確認されたら、影響範囲を特定し、関連する経路上の機器を順番に調査します。
例えば、pingやtracerouteで遅延が大きい区間を特定したり、パケットキャプチャ(Wiresharkなど)で通信内容を詳細に分析し、再送やウィンドウサイズの異常がないかを確認したりします。
● 冗長化設計の実装経験はありますか
ネットワーク機器の単一障害点をなくすため、VRRPやHSRPといったプロトコルを用いて、ルータやL3スイッチを冗長化した経験があります。
アクティブ機に障害が発生した場合、スタンバイ機が自動的に処理を引き継ぐ構成です。また、スイッチ間はリンクアグリゲーションで物理リンクを束ねて帯域を確保しつつ、1本のリンクが切れても通信が継続できるようにしました。
● 監視システムの構築経験はありますか
ZabbixやPrometheusといったオープンソースの監視ツールを用いて、ネットワーク監視システムを構築した経験があります。各ネットワーク機器の死活監視(ping)、リソース監視(SNMP)、トラフィック監視を行いました。
また、特定の閾値を超えた場合にアラート(メールやチャットツール)が通知されるように設定し、障害の早期発見と迅速な初動対応が可能になる体制を整えました。
● ネットワークセキュリティの脅威と対策について教えてください
代表的な脅威には、DDoS攻撃のようなサービス妨害、盗聴、なりすまし、不正アクセスなどがあります。対策としては、多層防御の考え方が重要です。
境界にはファイアウォールやIPS/IDSを設置して不正な通信をブロックし、内部ではVLANでセグメントを分割して被害の拡大を防ぎます。
また、通信はVPNやTLSで暗号化し、機器へのアクセスは認証を強化するとともに、操作ログを必ず取得して定期的に監査します。
● パフォーマンス低下時の調査手順はどうしていますか
まず、問題の影響範囲(特定のユーザーか、特定の拠点か、全体か)を切り分けます。
次に、ユーザー側からサーバー側へ向かって、pingやtracerouteでネットワーク経路上の遅延やパケットロスの有無を確認します。問題のありそうな区間が特定できたら、その区間のネットワーク機器の負荷状況やログを確認します。
ネットワークに問題がなければ、サーバーやアプリケーション側の問題も疑い、関連部署と連携して調査を進めます。
● 障害対応の優先順位はどう決めていますか
ビジネスインパクトの大きさで決めます。具体的には、「影響範囲の広さ(全社か、一部部署か)」と「業務の重要度(基幹システムか、情報系システムか)」の2つの軸で評価します。
例えば、全社で利用する基幹業務システムが停止している場合は最優先で対応します。
一方、影響範囲が限定的で、代替手段がある場合は、優先度を下げて対応することもあります。この判断基準は、事前にSLAなどで定義し、関係者と合意しておくことが重要です。
● 企業ネットワークの全体設計経験はありますか
従業員500名規模のオフィス移転に伴うネットワークの全体設計を担当しました。要件定義から機器選定、物理設計、論理設計までを一貫して行いました。
高可用性を実現するために、コアスイッチやインターネット回線を冗長化し、無線LAN環境では、電波干渉を考慮したAPの配置設計と、認証基盤(RADIUS)との連携を行いました。
また、将来的な拠点増加にも対応できるよう、拡張性のあるIPアドレッシング計画を策定しました。
● クラウドとオンプレのハイブリッド構成経験はあります
AWSとオンプレミスのデータセンターを専用線(AWS Direct Connect)で接続し、ハイブリッドクラウド環境を構築しました。オンプレミスにある基幹システムと、AWS上のWebシステムや分析基盤がセキュアに連携する構成です。
ルーティング設計や、両環境間でのIPアドレスの重複を避けるためのアドレス設計に注力しました。また、障害時に備え、バックアップとしてIPsec-VPN接続も構成しました。
● SDNの導入検討・実装経験はありますか
データセンターネットワークの運用効率化のため、SDN(Software-Defined Networking)の導入を検討・検証した経験があります。
物理的なネットワーク構成と、論理的なネットワーク構成を分離し、ソフトウェアで動的に制御することで、迅速なネットワークサービスの提供を目指しました。
特に、仮想マシンの追加や移動に合わせて、VLANやアクセスポリシーを自動的に設定するユースケースを中心に検証しました。実装には至りませんでしたが、コントローラベースの集中管理による運用負荷削減の可能性を実感しました。
● ネットワーク技術選定の判断基準は何ですか
技術的な要件を満たすことはもちろんですが、それに加えて運用性、標準化、TCO(総所有コスト) を重視します。特定のベンダーにロックインされないよう、できるだけ標準化された技術を採用します。
また、チームメンバーが学習・運用しやすいか、トラブルシューティングの情報が豊富にあるかといった運用性も重要です。初期の導入コストだけでなく、長期的なライセンス費用や保守、運用人件費まで含めたTCOを算出し、総合的に判断します。
● 運用自動化の推進経験はありますか
従来手作業で行っていたファイアウォールのポリシー変更や、スイッチのVLAN設定といった定型作業を、Ansibleを使って自動化する取り組みを推進しました。
設定情報をYAML形式のPlaybookでコードとして管理することで、誰が作業しても同じ結果になる構成の再現性を担保し、ヒューマンエラーを削減しました。また、設定変更の履歴がGitで管理できるため、構成管理と監査対応も効率化できました。
● チームメンバーの技術指導はどうしていますか
OJTを基本としつつ、体系的な知識も身につけられるよう支援します。
若手メンバーには、まず小規模なネットワークの構築や設定変更といったタスクを任せ、その設計や手順についてレビューを行います。その際に、なぜその設定が必要なのかという背景や、関連する技術知識も合わせて説明します。
また、定期的にチーム内で勉強会を開き、新しい技術トレンドや、過去に発生した障害の事例共有を行い、チーム全体の技術レベルの向上に努めています。
5-2.サーバーエンジニアの怒涛の技術質問18選
サーバーエンジニアの技術質問は以下の通りです。
- Linuxの基本コマンドは使えますか
- ファイルシステムと権限管理について教えてください
- プロセス管理とサービス管理の経験はありますか
- 仮想化技術の違いについて説明してください
- VMwareの操作経験はありますか
- Dockerの基本的な使用経験はありますか
- サーバーのパフォーマンス監視はどうしていますか
- バックアップ・リストア戦略はどう設計していますか
- ログ管理と解析はどうしていますか
- サーバーセキュリティ対策で何をしていますか
- AnsibleやChefの使用経験はありますか
- 自動化スクリプトの作成経験はありますか
- 大規模サーバーインフラの設計経験はありますか
- クラウド移行プロジェクトの推進経験はありますか
- 災害復旧戦略の設計・実装経験はありますか
- インフラ技術選定の意思決定プロセスはどうしていますか
- 運用チームの体制構築経験はありますか
- コスト最適化の実装経験はありますか
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
● Linuxの基本コマンドは使えますか
日常的に使用しています。ファイルの操作(ls, cp, mv, rm)、ディレクトリの移動(cd)、テキストの表示・編集(cat, less, vi)、権限の変更(chmod)、プロセスの確認(ps, top)、ネットワークの確認(ip, ss)といった基本的なコマンドは問題なく使えます。
また、パイプ(|)やリダイレクション(>, >>)を組み合わせて、コマンドの出力を加工することもできます。
● ファイルシステムと権限管理について教えてください
Linuxのファイルシステムは、ルートディレクトリ(/)を頂点とする階層構造になっています。
ファイルやディレクトリには、所有者、所有グループ、その他のユーザーに対して、それぞれ読み取り(r)、書き込み(w)、実行(x)の権限を設定できます。
ls -lコマンドで権限を確認し、chmodコマンドで変更します。例えば、chmod 755 script.shとすると、所有者は読み書き実行、グループとその他は読み取りと実行が可能になります。
● プロセス管理とサービス管理の経験はありますか
psやtopコマンドで実行中のプロセスを確認し、CPUやメモリを過剰に消費しているプロセスを特定した経験があります。不要なプロセスはkillコマンドで終了させます。
また、Webサーバー(Apache, Nginx)などの常駐プロセスは、systemdを使ってサービスとして管理します。
systemctl start/stop/restartでサービスの起動や停止、systemctl enable/disableでOS起動時の自動起動の有効・無効を設定した経験があります。
● 仮想化技術の違いについて説明してください
仮想化技術には、ホストOS型、ハイパーバイザー型、コンテナ型などがあります。
ホストOS型は、WindowsやmacOSといった既存のOS上に仮想化ソフトウェア(VMware Workstationなど)をインストールする方式です。
ハイパーバイザー型は、ハードウェア上に直接ハイパーバイザー(ESXiなど)をインストールし、その上で複数のゲストOSを動かす方式で、より高性能です。
コンテナ型(Dockerなど)は、OSレベルで環境を分離する技術で、ゲストOSが不要なため非常に軽量で高速に起動するのが特徴です。
● VMwareの操作経験はありますか
VMware vSphere環境の基本的な操作経験があります。
vCenter Serverに接続し、仮想マシンの新規作成、CPUやメモリ、ディスクといったリソースの割り当て変更、スナップショットの作成と復元、テンプレートからのデプロイといった一連の操作を行ったことがあります。
● Dockerの基本的な使用経験はありますか
Dockerfileを作成してWebアプリケーションのカスタムイメージをビルドし、そのイメージからコンテナを起動(docker run)した経験があります。
また、複数のコンテナ(WebサーバーとDBサーバーなど)を連携させるために、docker-composeを使って定義ファイル(docker-compose.yml)を記述し、一括で起動・停止する、といった開発環境の構築で利用しました。
● サーバーのパフォーマンス監視はどうしていますか
ZabbixやPrometheus、Grafanaといったツールを組み合わせて監視しています。CPU、メモリ、ディスクI/O、ネットワークトラフィックといった基本的なリソース監視はもちろん、アプリケーションのレスポンスタイムやエラーレートといったサービスレベルのメトリクスも取得します。
平常時の状態を把握し、異常を検知するためのアラート閾値は、単なる固定値ではなく、統計に基づいた動的な閾値や傾向を考慮して設定するようにしています。
● バックアップ・リストア戦略はどう設計していますか
まず、RPO(目標復旧時点)とRTO(目標復旧時間)を定義し、それに合わせて戦略を設計します。日次でフルバックアップ、時間単位で差分・増分バックアップを取得する、といった多世代のバックアップを基本とします。
バックアップデータは、サーバー本体とは物理的に異なる場所(別のストレージやクラウドストレージ)に保管し、災害対策も考慮します。
また、バックアップは取得するだけでなく、定期的にリストアテストを実施し、いざという時に確実に復旧できることを確認するのが重要です。
● ログ管理と解析はどうしていますか
FluentdやLogstashといったエージェントを使って、複数のサーバーからログを一元的なログ基盤(Elasticsearchなど)に集約します。
ログは、検索や集計がしやすいよう、JSONなどの構造化フォーマットで出力するようにアプリケーション側にも働きかけます。
収集したログは、Kibanaなどを用いて可視化・分析し、障害調査やセキュリティインシデントの追跡、サービスの利用状況分析などに活用します。
● サーバーセキュリティ対策で何をしています
多層防御を意識して対策しています。まず、OSやミドルウェアの脆弱性情報を常に収集し、セキュリティパッチを速やかに適用します。
不要なサービスやポートは停止・閉鎖し、攻撃の足がかりを減らします。また、ファイアウォール(iptables, firewalld)で不正なアクセスを制限し、パスワードポリシーの強化や多要素認証の導入で認証を固めます。
定期的な脆弱性スキャンを実施し、新たな脅威に対応することも欠かせません。
● AnsibleやChefの使用経験はありますか
Ansibleを用いた構成管理の経験があります。OSの初期設定、ミドルウェアのインストールと設定、ユーザー管理といった一連の作業をPlaybookとしてコード化しました。
これにより、手作業による設定ミスやサーバーごとの環境差異を防ぎ、インフラの再現性と一貫性を担保しました。また、設定変更のレビューや履歴管理がGit上でできるため、インフラの変更管理も効率化できました。
● 自動化スクリプトの作成経験はありますか
シェルスクリプトやPythonを使って、日々の運用業務を自動化するスクリプトを作成しました。
例えば、定期的なログのローテーションと圧縮、バックアップの取得と世代管理、サーバーのヘルスチェックと結果レポートの通知といった定型作業を自動化し、運用負荷の軽減とヒューマンエラーの削減に貢献しました。
● 大規模サーバーインフラの設計経験はありますか
数百万ユーザーが利用するWebサービスのインフラ設計を担当しました。
高トラフィックを捌くため、ロードバランサー配下でWebサーバーとAPサーバーを水平スケールさせる構成としました。DBは、書き込み負荷を考慮してプライマリを、参照負荷を考慮して複数のリードレプリカを配置する構成です。
また、画像などの静的コンテンツはCDNから配信し、頻繁にアクセスされるデータはRedisクラスタでキャッシュすることで、システム全体のパフォーマンスと可用性を高めました。
● クラウド移行プロジェクトの推進経験はありますか
オンプレミスで稼働していた物理サーバー数十台規模のシステムを、AWSへ移行するプロジェクトをリーダーとして推進しました。
まず、既存システムの資産を棚卸しし、単純なリフト&シフトで移行するものと、クラウドネイティブなサービス(RDS, S3など)を活用してリファクタリングするものを切り分けました。
移行計画を策定し、Terraformを用いてAWS環境をコードで構築しました。データ移行や切り替え手順を綿密に計画・リハーサルすることで、サービス停止時間を最小限に抑えた移行を実現しました。
● 災害復旧(DR)戦略の設計・実装経験はありますか
本番環境とは地理的に離れたリージョンにDRサイトを構築しました。データベースは非同期レプリケーションで常に同期し、アプリケーションサーバーの構成はAMI(Amazon Machine Image)として定期的にバックアップしました。
障害発生時には、DNSの向き先をDRサイトに切り替えることで、事業を継続できる仕組みです。
RPOとRTOを定義し、それに基づいた復旧手順書を作成し、定期的なDR訓練を実施して手順の有効性を確認しました。
● インフラ技術選定の意思決定プロセスはどうしていますか
まず、解決したい課題(コスト、パフォーマンス、運用性など)を明確にします。次に、複数の技術やサービスを候補として挙げ、機能、コスト、学習曲線、将来性、コミュニティのサポート体制などの観点で比較評価します。
この評価はドキュメントにまとめ、チームやステークホルダーと共有・議論します。
重要な選定では、PoC(概念実証)を実施して技術的なリスクや実際の性能を評価した上で、最終的な意思決定を行います。決定理由とプロセスは必ず記録に残し、透明性を確保します。
● 運用チームの体制構築経験はありますか
SRE(Site Reliability Engineering)の考え方に基づいた運用チームの体制構築を経験しました。SLI/SLOを定義してサービスの信頼性を定量的に管理し、エラーバジェットの範囲内で開発と運用のバランスを取る仕組みを導入しました。
また、運用業務(トイル)の削減を目標に掲げ、自動化を積極的に推進しました。
障害対応では、非難の文化をなくし、ポストモーテムを通じて根本原因の分析と再発防止策の検討を行うプロセスを定着させ、継続的な改善を促しました。
● コスト最適化の実装経験はありますか
クラウド環境のコスト最適化に取り組みました。まず、AWS Cost Explorerなどでコストを可視化し、どのサービスやリソースにコストがかかっているかを分析しました。
その上で、不要なリソースの停止・削除、トラフィックの増減に合わせたAuto Scalingの導入、より安価なインスタンスタイプへの変更、リザーブドインスタンスやSavings Plansの活用などを実施しました。
また、各開発チームにコスト意識を持ってもらうため、タグ付けを徹底し、チームごとのコストをダッシュボードで見える化する取り組みも行いました。
5-3.クラウドエンジニアの怒涛の技術質問18選
クラウドエンジニアの技術質問は以下の通りです。
- AWS、Azure、GCPの主要サービスの違いは何ですか
- VPCの設計・構築経験はありますか
- IAMの権限設定はどうしていますか
- Auto Scalingの設定経験はありますか
- クラウドストレージサービスの使い分けはどうしていますか
- コスト監視はどうしていますか
- マルチクラウド環境の設計経験はありますか
- Kubernetesの運用経験はありますか
- CI/CDパイプラインのクラウド実装経験はありますか
- クラウドセキュリティの実装経験はありますか
- データ保護とプライバシー対策はどうしていますか
- コンプライアンス管理の経験はありますか
- 大規模クラウド移行プロジェクトの責任者経験はありますか
- ハイブリッドクラウドの設計・運用経験はありますか
- クラウドネイティブアプリケーションの設計経験はありますか
- クラウド戦略の立案・実行経験はありますか
- 組織のクラウド化推進経験はありますか
- 技術的負債の解消とモダナイゼーション経験はありますか
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
● AWS、Azure、GCPの主要サービスの違いは何ですか
3大クラウドともに仮想サーバー、ストレージ、データベースといった基本的なサービスは提供していますが、それぞれに特徴があります。
AWSは最も歴史が長く、サービスの数と種類が豊富で、ドキュメントや事例も多いため、汎用的に使いやすいです。
Azureは、Windows ServerやMicrosoft 365といったマイクロソフト製品との親和性が高く、エンタープライズ領域に強みがあります。
GCPは、KubernetesやBigQueryといったコンテナ技術やデータ分析・機械学習系のサービスに強みがあるという印象です。
● VPCの設計・構築経験はありますか
AWSでWebアプリケーションを構築する際に、VPCを設計・構築しました。外部に公開するWebサーバーを配置するパブリックサブネットと、DBサーバーなどを配置するプライベートサブネットに分割しました。
パブリックサブネットにはインターネットゲートウェイを、プライベートサブネットからはNATゲートウェイ経由で外部にアクセスできるように設定しました。
また、セキュリティグループとネットワークACLを使って、サブネット間やインスタンスへのアクセスを適切に制御しました。
● IAMの権限設定はどうしていますか
最小権限の原則に従って設定します。まず、IAMユーザーやIAMロールを作成し、必要な権限だけを記述したIAMポリシーをアタッチします。
個々のユーザーに直接ポリシーをアタッチするのではなく、職務に応じたIAMグループを作成し、ユーザーをグループに所属させることで、権限管理を効率化します。
EC2インスタンスなどから他のAWSサービスにアクセスする場合は、アクセスキーを直接埋め込むのではなく、IAMロールをインスタンスに割り当てる方法を取ります。
● Auto Scalingの設定経験はありますか
Webサーバーの負荷に応じてインスタンス数を自動で増減させるため、Auto Scalingグループを設定しました。
CPU使用率をトリガーとし、例えば「CPU使用率が5分間継続して70%を超えたらインスタンスを1台追加する」といったスケーリングポリシーを定義しました。
また、予期せぬトラフィック急増に備え、最小インスタンス数と最大インスタンス数を設定し、コストの無駄遣いやサービスの停止を防ぐようにしました。
● クラウドストレージサービスの使い分けはどうしていますか
用途に応じて使い分けます。画像や動画、ログファイルといったアクセス頻度は低いが大量のデータを安価に保存したい場合は、Amazon S3やAzure Blob Storageのようなオブジェクトストレージを使います。
EC2インスタンスにアタッチしてOSやアプリケーションのファイルシステムとして使いたい場合は、Amazon EBSやAzure Disk Storageのようなブロックストレージを使います。
複数のインスタンスから同時にアクセスする共有ファイルサーバーが必要な場合は、Amazon EFSやAzure Filesのようなファイルストレージを選択します。
● コスト監視はどうしていますか
AWS Budgetsを使って、月間の予算を設定し、予算を超過しそうになったらアラートが通知されるようにしています。
また、AWS Cost Explorerを使って、日々のコストの推移や、サービスごとのコスト内訳を確認し、意図しないコスト増がないかを定期的にチェックしています。
リソースには、プロジェクト名や部署名といったタグを付けることを徹底し、どのリソースがどれだけコストを使っているかを追跡しやすくしています。
● マルチクラウド環境の設計経験はありますか
システムの可用性向上とベンダーロックインの回避を目的として、AWSとGCPを用いたマルチクラウド環境を設計しました。
主要なアプリケーションは両方のクラウドで稼働させ、DNSレベルで負荷分散と障害時の切り替えを行いました。
データベースは、クラウド間でレプリケーションが可能なマネージドサービスを選定しました。インフラのプロビジョニングには、両方のクラウドに対応できるTerraformを使用し、構成管理の一元化を図りました。
● Kubernetesの運用経験はありますか
AWSのマネージドサービスであるEKSを用いて、本番環境でKubernetesクラスタを運用した経験があります。
アプリケーションのデプロイやスケーリング、ローリングアップデートなどをkubectlコマンドやマニフェストファイル(YAML)で管理しました。
また、PrometheusとGrafanaを導入してクラスタやPodのリソース監視を行い、Fluentdでログを収集・分析する基盤も構築しました。HPA(Horizontal Pod Autoscaler)による自動スケーリングも設定しました。
● CI/CDパイプラインのクラウド実装経験はあります
GitHub ActionsとAWSの各種サービスを連携させたCI/CDパイプラインを実装しました。
開発者がコードをプッシュすると、GitHub Actionsがコンテナイメージをビルドし、ECR(Elastic Container Registry)にプッシュします。
その後、CodeDeployと連携して、ECS(Elastic Container Service)やEKS上のアプリケーションをBlue/Greenデプロイメント方式で安全に更新する、という一連の流れを自動化しました。
● クラウドセキュリティの実装経験はありますか
AWS WAFを導入してWebアプリケーションへのSQLインジェクションやXSS攻撃を防ぎ、GuardDutyで予期せぬAPIコールや不正なアクティビティを検知する仕組みを構築しました。
また、VPC Flow LogsやCloudTrailのログを分析し、不審な通信や操作がないかを監視しました。
IAMポリシーを定期的に見直し、最小権限の原則が守られているかを確認することも重要な業務でした。
● データ保護とプライバシー対策はどうしていますか
まず、データを重要度に応じて分類し、保護レベルを定義します。
個人情報などの機密データは、AWS KMS(Key Management Service)を使って暗号化キーを管理し、保管時(S3, RDSなど)と転送時(TLS)の両方で暗号化を徹底します。
データへのアクセスは、IAMポリシーで厳格に制御し、誰がいつアクセスしたかをCloudTrailのログで追跡できるようにします。また、GDPRなどのプライバシー規制に対応するため、データの所在地や保持期間の管理にも注意を払います。
● コンプライアンス管理の経験はありますか
PCI DSSやISMS(ISO 27001)といったセキュリティ基準への準拠が求められるシステムを担当した経験があります。AWS Artifactでコンプライアンスレポートを確認し、クラウド側の責任範囲を把握しました。
その上で、AWS Configを用いて、リソースの設定がセキュリティポリシーに準拠しているかを継続的にチェックし、違反があった場合は自動的に通知・修正される仕組みを構築しました。
また、監査人からの要求に応じて、必要なログや設定情報を提出する対応も行いました。
● 大規模クラウド移行プロジェクトの責任者経験はありますか
オンプレミスで稼働していた数百台規模のシステム群をAWSへ全面的に移行するプロジェクトで、インフラ側の責任者を務めました。
移行戦略の策定から関わり、アプリケーションの特性に応じて7つのR(Rehost, Replatform, Refactorなど)を使い分ける方針を立てました。
インフラ設計、データ移行計画、セキュリティ設計、そして切り替え後の運用体制の構築までを統括しました。プロジェクト管理ツールを用いて進捗を管理し、定期的に経営層へ報告を行いました。
● ハイブリッドクラウドの設計・運用経験はありますか
個人情報など機密性の高いデータはオンプレミスに残しつつ、スケーラビリティが求められるWeb/AP層はクラウドに配置する、というハイブリッドクラウド環境を設計・運用しました。
オンプレミスとクラウド間は、専用線とIPsec-VPNによる冗長化されたネットワークで接続しました。両環境にまたがるID管理を統合するため、Active DirectoryとクラウドのID管理サービスを連携させ、シングルサインオンを実現しました。
● クラウドネイティブアプリケーションの設計経験はありますか
マイクロサービス、コンテナ、サーバーレスといったクラウドネイティブ技術を全面的に採用したアプリケーションのアーキテクチャ設計を経験しました。
各機能は独立したコンテナ(Docker)として実装し、Kubernetes(EKS)上でオーケストレーションしました。
また、非同期処理やイベント連携には、LambdaやSQS、EventBridgeといったサーバーレスサービスを積極的に活用し、疎結合でスケーラブルなシステムを実現しました。
インフラはTerraformですべてコード化し、オブザーバビリティの確保にも注力しました。
● クラウド戦略の立案・実行経験はありますか
全社的なクラウド活用を推進するため、クラウド戦略の立案から実行までを担当しました。まず、経営課題や事業戦略をヒアリングし、それを解決するためにクラウドをどう活用できるかを検討しました。
その上で、「クラウドファースト」の方針を掲げ、クラウド利用のガイドラインや、セキュリティ基準、コスト管理のルールなどを定めたCCoE(Cloud Center of Excellence)という専門組織の立ち上げを主導しました。
● 組織のクラウド化推進経験はありますか
CCoEのリーダーとして、組織全体のクラウド化を推進しました。各事業部のエンジニアに対して、クラウドの基礎知識やハンズオン形式のトレーニングを実施し、クラウド人材の育成に努めました。
また、各プロジェクトが円滑にクラウドを利用できるよう、共通で使えるTerraformモジュールやCI/CDパイプラインといった「ガードレール」を整備しました。
定期的に成功事例を社内で共有し、クラウド活用のメリットを啓蒙することで、ボトムアップでの活用も促進しました。
● 技術的負債の解消とモダナイゼーション経験はありますか
オンプレミスのレガシーな仮想サーバー上で稼働していたアプリケーションを、クラウドネイティブなアーキテクチャへモダナイズするプロジェクトを推進しました。
単純なリフト&シフトではなく、アプリケーションをマイクロサービスとして再設計・分割し、インフラをコンテナ化(Docker/Kubernetes)しました。
手作業でのデプロイや設定変更といった技術的負債を解消するため、CI/CDパイプラインとInfrastructure as Codeを導入し、開発から運用までのプロセス全体を刷新しました。
5-4.データベースエンジニアの怒涛の技術質問18選
- SQLの基本的な最適化はできますか
- インデックスの設計・運用経験はありますか
- バックアップとリストアの実装経験はありますか
- トランザクション管理について教えてください
- レプリケーションの設定経験はありますか
- データベース監視はどうしていますか
- パフォーマンス チューニングの経験はありますか
- パーティショニングの設計・実装経験はありますか
- 高可用性の実装経験はありますか
- データ移行プロジェクトの経験はありますか
- 容量計画はどうしていますか
- 障害対応の経験について教えてください
- 大規模データベースの設計・運用経験はありますか
- シャーディングの設計・実装経験はありますか
- データベースアーキテクチャの選定経験はありますか
- データガバナンスの実装経験はありますか
- データベースチームの技術指導経験はありますか
- データベース戦略の立案経験はありますか
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
● SQLの基本的な最適化はできますか
まずEXPLAINで実行計画を確認し、Full Table Scanが発生していないか、インデックスが効果的に使われているかを見ます。WHERE句で頻繁に検索条件となるカラムや、JOINの結合キーとなるカラムにはインデックスを作成します。
また、SELECT *は避け、必要なカラムのみを指定します。ORをUNIONで書き換えたり、サブクエリをJOINに書き換えたりすることで、パフォーマンスが改善する場合があることも理解しています。
● インデックスの設計・運用経験はありますか
アプリケーションのクエリを分析し、検索条件やソートで頻繁に使用されるカラムに対してB-Treeインデックスを作成しました。
複数のカラムを条件にすることが多い場合は、複合インデックスを作成し、カーディナリティの高いカラムを先頭に配置するよう設計しました。
運用では、定期的にインデックスの使用状況を監視し、使われていない不要なインデックスは削除することで、書き込み性能の劣化を防ぎました。
● バックアップとリストアの実装経験はありますか
mysqldumpやpg_dumpといったツールを使い、データベースの論理バックアップを取得するスクリプトを作成・運用した経験があります。cronで定期的に日次フルバックアップを取得し、世代管理を行いました。
また、障害を想定したリストア訓練として、バックアップファイルから別のテスト環境にデータベースを復元する手順を確認し、ドキュメント化しました。
● トランザクション管理について教えてください
トランザクションは、ACID特性(原子性、一貫性、独立性、永続性)を持つ一連の処理の単位です。複数の更新処理をまとめることで、処理全体が成功するか失敗するかのどちらかであることが保証されます。
分離レベル(Isolation Level)についても理解しており、ダーティリードやファントムリードといった問題を防ぐために、READ COMMITTEDやREPEATABLE READといったレベルを適切に設定する必要があることを認識しています。
● レプリケーションの設定経験はありますか
MySQLの非同期レプリケーションを設定した経験があります。プライマリサーバーの更新履歴(バイナリログ)を、複数のリードレプリカサーバーが読み取り、自身のデータに反映させる構成です。
これにより、参照系のクエリをレプリカに分散させ、プライマリの負荷を軽減しました。レプリケーションの遅延を監視し、問題が発生した際にはログを確認して原因を調査しました。
● データベース監視はどうしていますか
データベースのマネージドサービス(AWS RDSなど)が提供する監視機能(CloudWatch Metrics)を利用していました。
CPU使用率、メモリ空き容量、ディスクI/O、DBコネクション数といった基本的なメトリクスを監視し、閾値を超えた場合にアラートが飛ぶように設定しました。
また、スロークエリログを有効にし、実行に時間がかかっているクエリを定期的に確認して、パフォーマンス改善の対象を特定していました。
● パフォーマンス チューニングの経験はありますか
スロークエリログやAPMツールからボトルネックとなっているクエリを特定し、EXPLAINで実行計画を詳細に分析しました。
インデックスの追加や見直し、クエリの書き換え(サブクエリのJOINへの変更など)といった基本的な対策に加え、データベースのパラメータチューニング(バッファプールサイズなど)や、テーブル設計の見直し(非正規化の検討など)まで踏み込んで改善を行った経験があります。
● パーティショニングの設計・実装経験はありますか
数億件のレコードを持つ巨大なログテーブルに対して、パフォーマンスと運用性の向上のためにパーティショニングを実装しました。
日付をキーにしたレンジパーティショニングを採用し、月ごとにテーブルを物理的に分割しました。
これにより、期間を指定した検索のパフォーマンスが大幅に向上し、古い月のパーティションを丸ごと削除・バックアップするといった運用も容易になりました。
● 高可用性の実装経験はありますか
PostgreSQLのストリーミングレプリケーションを用いて、アクティブ・スタンバイ構成による高可用性構成を構築しました。
プライマリサーバーに障害が発生した際に、スタンバイサーバーに自動的にフェイルオーバーする仕組みです。フェイルオーバーの検知と実行には、Pacemakerやpgpool-IIといったクラスタ管理ソフトウェアを利用しました。
また、仮想IP(VIP)を使い、アプリケーション側は接続先DBを意識することなく、常に単一のエンドポイントにアクセスできる構成にしました。
● データ移行プロジェクトの経験はありますか
オンプレミスのOracleデータベースから、AWSのAurora(PostgreSQL互換)へデータ移行するプロジェクトを担当しました。
AWS DMS(Database Migration Service)を利用し、サービス停止時間を最小限に抑えるため、初期データの一括ロード後、継続的な差分レプリケーション(CDC)を行う方式を取りました。
移行前には、データ型や文字コードの違い、ストアドプロシージャの互換性などを十分に調査し、テスト環境で入念なリハーサルを繰り返しました。
● 容量計画はどうしていますか
現在のデータ増加率と、将来の事業計画(ユーザー数の増加予測など)を基に、将来のディスク使用量を予測します。監視ツールで日々のデータ増加量を記録・グラフ化し、その傾向から、例えば「半年後にはディスク使用率が80%に達する」といった予測を立てます。
そして、アラートの閾値を設定し、ディスク容量が枯渇する前に、スケールアップや不要データのアーカイブといった対策を計画的に実施できるようにします。
● 障害対応の経験について教えてください
データベースの高負荷により、サービス全体が遅延する障害に対応した経験があります。まず、SHOW PROCESSLISTなどで実行中のクエリを確認し、原因となっている長時間実行クエリを特定しました。
そのクエリをKILLして応急処置を行った後、根本原因を調査しました。原因は、特定の検索条件でインデックスが効かなくなるケースがあることでした。
恒久対策として、クエリを修正し、適切なインデックスを追加することで再発を防止しました。
● 大規模データベースの設計・運用経験はありますか
テラバイト級のデータを扱うDWH(データウェアハウス)の設計・運用を経験しました。
大量データのバッチロードと、複雑な集計クエリのパフォーマンスを両立させるため、カラムナーストレージ型のデータベース(Amazon Redshiftなど)を採用しました。
データモデルはスタースキーマで設計し、分散キーやソートキーを適切に設定することで、JOINや集計処理の効率を最大化しました。
また、マテリアライズドビューを活用し、頻繁に実行される集計結果を事前に計算しておくことで、クエリの応答速度を向上させました。
● シャーディングの設計・実装経験はありますか
書き込み負荷が非常に高く、単一のプライマリサーバーでは捌ききれないシステムにおいて、シャーディングを設計・実装しました。
ユーザーIDをシャーディングキーとし、ハッシュ値に基づいてデータを複数のシャード(DBサーバー群)に分散させる方式です。アプリケーション層で、シャーディングキーに応じて接続先のシャードを決定するロジックを実装しました。
シャードをまたいだ検索や集計が複雑になるという課題に対しては、一部のデータを非正規化して各シャードに持たせるなどの工夫を行いました。
● データベースアーキテクチャの選定経験はありますか
新規サービスの立ち上げ時に、データベースアーキテクチャの選定を担当しました。
サービスの特性(トランザクション要件、データ構造、スケーラビリティ要件など)を分析し、RDBMS、NoSQL(キーバリュー、ドキュメント、カラムナなど)、NewSQLといった複数の選択肢を比較検討しました。
それぞれのメリット・デメリット、運用コスト、将来性を評価し、PoCを実施した上で、最終的にサービスのコア機能にはRDBMSを、ログなどの揮発性の高いデータにはNoSQLを組み合わせる、ポリグロットパーシステンスのアプローチを提案・採用しました。
● データガバナンスの実装経験はありますか
全社的なデータ活用を推進するため、データガバナンスの体制構築に携わりました。まず、社内に散在するデータの所在や意味を定義したデータカタログを整備しました。
次に、データの品質を維持するためのルール(データクオリティマネジメント)や、個人情報保護法などの法令を遵守するためのデータセキュリティポリシーを策定しました。
そして、データスチュワードという各部署のデータ責任者を任命し、これらのルールが遵守されるよう、組織横断で働きかけました。
● データベースチームの技術指導経験はありますか
DBAチームのリーダーとして、メンバーの育成に努めました。SQLのアンチパターンや、インデックスのベストプラクティスといった技術的な知識を共有する勉強会を定期的に開催しました。
また、各メンバーのスキルレベルやキャリア志向に合わせて、パフォーマンスチューニングやアーキテクチャ設計といった挑戦的なタスクをアサインし、1on1を通じてサポートしました。
障害対応の際には、根本原因の分析プロセスを共に進めることで、実践的なトラブルシューティング能力の向上を促しました。
● データベース戦略の立案経験はありますか
全社のデータベース基盤に関する中期的な戦略を立案した経験があります。
現状の各システムの課題(コスト、パフォーマンス、運用負荷など)を分析し、将来の事業成長を見据えた上で、「クラウドのマネージドサービスの積極活用」「特定ベンダーへの依存度低減(OSSへの移行)」「データベース運用の自動化・セルフサービス化」といった方針を策定しました。
この戦略を経営層に提案し、承認を得て、具体的なロードマップに落とし込み、実行を推進しました。
5-5.セキュリティエンジニアの怒涛の技術質問18選
- 情報セキュリティの3要素について説明してください
- 主要な脅威とその対策について教えてください
- ファイアウォールの設定・運用経験はありますか
- ログ監視とインシデント対応の経験はありますか
- 脆弱性スキャンの実施経験はありますか
- セキュリティポリシーの運用経験はありますか
- セキュリティアーキテクチャの設計経験はありますか
- 侵入検知・防御システムの構築経験はありますか
- セキュリティ教育の実施経験はありますか
- リスクアセスメントの実施経験はありますか
- コンプライアンス対応の経験はありますか
- インシデント対応計画の策定経験はありますか
- 組織のセキュリティ戦略立案経験はありますか
- セキュリティ組織の構築・運営経験はありますか
- 経営層への報告とリスクコミュニケーション経験はありますか
- 脅威ハンティングの実装経験はありますか
- ゼロトラストアーキテクチャの設計経験はありますか
- AI/MLを活用したセキュリティ対策の経験はありますか
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
● 情報セキュリティの3要素について説明してください
情報セキュリティの3要素は、機密性(Confidentiality)、完全性(Integrity)、可用性(Availability)で、頭文字をとってCIAと呼ばれます。
機密性は、認可された者だけが情報にアクセスできること。完全性は、情報が正確かつ完全な状態で、改ざんされていないこと。可用性は、認可された者が、必要な時にいつでも情報にアクセスできることです。
これら3つのバランスを保つことが重要です。
● 主要な脅威とその対策について教えてください
主要な脅威として、マルウェア感染、標的型攻撃、Webアプリケーションの脆弱性を狙った攻撃(SQLインジェクション、XSSなど)が挙げられます。
対策として、マルウェアにはアンチウイルスソフトの導入と定義ファイルの更新。標的型攻撃には、不審なメールを開かないといった従業員教育と、多層防御の考え方が有効です。
Webの脆弱性には、セキュアコーディングの実践と、WAF(Web Application Firewall)の導入が効果的です。
● ファイアウォールの設定・運用経験はありますか
ネットワークの境界に設置されたファイアウォールで、アクセスコントロールリスト(ACL)を運用していました。
外部から内部への通信は、原則すべて拒否し、Webサーバーの公開に必要なポートなど、許可された通信のみを通す設定(デフォルトDeny)です。
また、社内から外部への通信についても、業務上不要なポートは閉じるようにしていました。設定変更の際は、申請内容をレビューし、影響範囲を確認した上で作業を行いました。
● ログ監視とインシデント対応の経験はありますか
SIEM(Security Information and Event Management)ツールを使い、ファイアウォールやサーバー、プロキシなど、様々な機器のログを監視していました。
SIEMで検知されたアラート(例:短時間に大量のログイン失敗)に対し、インシデントと判断した場合は、手順書に従って初動対応を行いました。具体的には、影響範囲の特定、通信の遮断、関連部署への報告などです。
● 脆弱性スキャンの実施経験はありますか
NessusやOpenVASといった脆弱性スキャンツールを使い、社内のサーバーやネットワーク機器に対して定期的にスキャンを実施していました。
スキャン結果のレポートを分析し、発見された脆弱性の危険度(CVSSスコアなど)を評価します。そして、各システムの担当者と連携し、パッチ適用や設定変更といった対策の計画を立て、実施を依頼・追跡しました。
● セキュリティポリシーの運用経験はありますか
情報セキュリティポリシーに基づいた運用業務を経験しました。
例えば、パスワードポリシーに従って、定期的なパスワード変更をユーザーに促したり、複雑性の要件を満たさないパスワードが設定できないようにシステム側で制御したりしました。
また、PCの資産管理台帳を更新したり、ソフトウェアのインストール申請をポリシーに照らして承認したりといった業務も担当しました。
● セキュリティアーキテクチャの設計経験はありますか
新規Webサービスの立ち上げに際し、セキュリティアーキテクチャの設計を担当しました。
ゼロトラストの考え方に基づき、境界防御に頼るのではなく、すべての通信を検証・暗号化することを基本方針としました。
具体的には、WAF、IPS/IDSによる多層防御、厳格なID管理と多要素認証、マイクロセグメンテーションによる内部通信の制御、詳細なログ取得と監視といった要素を組み合わせて、堅牢なシステムを設計しました。
● 侵入検知・防御システムの構築経験はありますか
オープンソースのSnortやSuricataを用いて、NIDS(ネットワーク型侵入検知システム)を構築した経験があります。
ネットワークのミラーポートからトラフィックを収集し、既知の攻撃パターン(シグネチャ)に一致する通信や、通常とは異なる振る舞い(アノマリ)を検知してアラートを出す仕組みです。
検知精度を高めるため、シグネチャのチューニングや、誤検知の分析を継続的に行いました。
● セキュリティ教育の実施経験はありますか
全従業員を対象としたセキュリティ教育を企画・実施しました。
標的型攻撃メールの訓練では、実際に疑似的な攻撃メールを送付し、開封率やURLのクリック率を測定して、組織のセキュリティ意識レベルを可視化しました。
その結果を基に、具体的な手口や見分け方のポイントを解説する研修会を実施し、全社的なリテラシー向上に貢献しました。
● リスクアセスメントの実施経験はありますか
まず、保護すべき情報資産(顧客情報、技術情報など)を洗い出し、それぞれの資産に対する脅威(不正アクセス、紛失など)と脆弱性を特定しました。
そして、それらの脅威が発生する可能性と、発生した場合のビジネスへの影響度をマトリクスで評価し、リスクレベルを算定しました。
その結果に基づき、受容できない高リスクな項目については、具体的な対策計画を立案し、経営層に報告しました。
● コンプライアンス対応の経験はありますか
ISMS(ISO 27001)認証の取得・更新プロジェクトに携わりました。
規格の要求事項と、自社のセキュリティ対策状況とのギャップを分析し、不足している規程や手順書の作成、運用記録の整備を行いました。
また、内部監査員として各部署の準拠状況をチェックしたり、外部審査員の監査に対応したりした経験があります。
● インシデント対応計画の策定経験はありますか
CSIRT(Computer Security Incident Response Team)のメンバーとして、インシデント対応計画の策定と改訂に携わりました。
インシデントの発見から、初動対応、封じ込め、根絶、復旧、そして事後対応(報告、再発防止策)までの一連のフェーズを定義しました。
また、インシデントの深刻度に応じた報告体制や、各部署の役割分担を明確にし、サイバー攻撃演習を通じて計画の実効性を定期的に評価・改善しました。
● 組織のセキュリティ戦略立案経験はありますか
セキュリティ部門の責任者として、中期的なセキュリティ戦略を立案しました。経営戦略や事業計画、そして最新の脅威動向や技術トレンドを踏まえ、「ゼロトラストアーキテクチャへの移行」「セキュリティ運用の自動化(SOAR)」「全社的なセキュリティ人材の育成」といった重点戦略を策定しました。
各戦略の具体的なロードマップとKPIを設定し、経営会議で承認を得て、実行を推進しました。
● セキュリティ組織の構築・運営経験はありますか
CSIRTの立ち上げを主導した経験があります。まず、組織内でのCSIRTのミッションと役割を定義し、経営層から承認を得ました。
次に、インシデントハンドリング、脆弱性管理、脅威情報分析といった機能ごとに必要なスキルセットを定義し、社内の各部署からメンバーを招集してチームを組成しました。
そして、インシデント対応プロセスや情報共有のルールを整備し、チームの運営を軌道に乗せました。
● 経営層への報告とリスクコミュニケーション経験はありますか
四半期に一度、CISOとして経営会議でセキュリティ状況を報告していました。
インシデントの発生状況や脆弱性対応の進捗といった運用状況に加え、それらがビジネスに与えるリスクを、専門用語を避け、金銭的な影響などに換算して説明することを心がけました。
また、新たなセキュリティ投資を提案する際には、対策を講じなかった場合のリスクと、投資によって得られるリスク低減効果を明確に示し、経営判断を仰ぎました。
● 脅威ハンティングの実装経験はありますか
従来の受動的なアラート監視に加え、潜在的な脅威を能動的に発見するための脅威ハンティングを実装しました。
EDR(Endpoint Detection and Response)やSIEMに蓄積された膨大なログデータに対し、「攻撃者はどのような痕跡を残すか」という仮説を立て、それを検証するためのクエリを実行・分析しました。
例えば、「正規のプロセスに偽装した不審な通信」や「深夜の管理者権限でのアクセス」といった仮説に基づき、攻撃の兆候を早期に発見することに成功しました。
● ゼロトラストアーキテクチャの設計経験はありますか
従来の境界型防御モデルからの脱却を目指し、ゼロトラストアーキテクチャへの移行を設計・推進しました。
ID管理を基盤とし、すべてのユーザーとデバイスを厳格に認証・認可するIDaaS(Identity as a Service)を導入しました。
また、社内ネットワークであっても信用せず、すべてのアクセスに対して、その都度コンテキスト(誰が、どのデバイスで、どこから、何に)に応じた動的なアクセスコントロールを行う仕組みを設計しました。
● AI/MLを活用したセキュリティ対策の経験はありますか
UEBA(User and Entity Behavior Analytics)製品を導入し、AI/MLを活用した異常検知の高度化に取り組みました。
平常時のユーザーやエンティティの振る舞いを機械学習し、それから逸脱する行動(例:深夜の大量データダウンロード、普段アクセスしないサーバーへのアクセス)を自動的に検知するものです。
これにより、従来のシグネチャベースの検知では見逃してしまうような、未知の脅威や内部不正の兆候を捉えることが可能になりました。
6.エンジニアとしての実務経験を問う怒涛の質問16選
よくある3つのパターンで聞かれる質問についてまとめました。
- プロジェクト管理・リーダーシップの質問6選
- 技術選定・意思決定の質問6選
- チーム・組織での働き方の質問6選
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
6-1.プロジェクト管理・リーダーシップの質問6選
プロジェクト管理やリーダーシップに関する質問は以下の通りです。
- これまでで最も困難だったプロジェクトは何ですか
- チームメンバーとの技術的な意見の相違はどう解決しましたか
- プロジェクトの遅延が発生した時の対応は何をしましたか
- 技術的負債の管理と解消はどう進めましたか
- ステークホルダーとの技術的な調整経験はありますか
- プロジェクトの成功要因は何だと思いますか
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
● これまでで最も困難だったプロジェクトは何ですか
前職で担当した、10年以上稼働している基幹システムを刷新するプロジェクトが最も困難でした。
困難だった理由は、ドキュメントがほとんど残っておらず、現行システムの仕様がブラックボックス化していた点です。
まず、現行システムのソースコードやデータ、そして長年運用してきた担当者へのヒアリングを通じて、徹底的に仕様を洗い出すことから始めました。
その上で、影響範囲の大きい機能から段階的にリリースする計画を立て、新旧システムを併存させながら慎重に移行を進めることで、無事にプロジェクトを完遂することができました。
この経験から、不確実性の高い状況で、地道な調査と計画的なリスク管理がいかに重要であるかを学びました。
● チームメンバーとの技術的な意見の相違はどう解決しましたか
技術選定の際に、メンバー間で意見が分かれた経験があります。一方は実績のある枯れた技術を、もう一方は生産性の高い新しい技術を主張していました。
私はまず、両者の意見を客観的に評価するため、それぞれの技術のメリット・デメリット、学習コスト、将来性などをまとめた比較表を作成しました。
そして、感情的な対立にならないよう、あくまで「プロジェクトの成功」という共通の目的に立ち返ることを促しました。
その上で、比較表を基に、今回のプロジェクト要件に最も合致するのはどちらかを冷静に議論し、最終的にはチーム全員が納得する形で結論を出すことができました。
● プロジェクトの遅延が発生した時の対応は何をしましたか
プロジェクト中盤で、特定メンバーの担当タスクに想定外の技術的課題が発覚し、遅延が発生しました。
私はまず、リーダーとして状況を正確に把握し、遅延がプロジェクト全体に与える影響を再評価しました。その上で、課題解決のために別のメンバーを一時的にアサインし、ペアプログラミングで集中的に対応しました。
同時に、後続タスクの依存関係を見直し、遅延の影響を受けないタスクを先に進めるよう、計画を柔軟に調整しました。
そして、クライアントには状況を正直に報告し、現実的なリカバリープランを提示することで、信頼関係を損なうことなく乗り切ることができました。
● 技術的負債の管理と解消はどう進めましたか
まず、コードの複雑度を計測するツールや、チームメンバーからのヒアリングを通じて、既存の技術的負債をリストアップし、可視化しました。
次に、それぞれの負債がビジネスに与える影響(障害リスク、開発速度の低下など)と、解消にかかる工数を評価し、優先順位付けを行いました。
そして、機能開発を完全に止めるのではなく、スプリントごとに開発リソースの20%を技術的負
債の返済に充てる、というルールをチームで合意し、計画的に解消を進めました。
● ステークホルダーとの技術的な調整経験はありますか
営業部門から「AIを使った新機能をすぐに追加してほしい」という要望がありましたが、技術的な実現性や開発工数を考慮すると、すぐには難しい状況でした。
私は、AIの仕組みや、導入に必要なデータ、開発ステップなどを、専門用語を避けて分かりやすく説明する資料を作成し、営業部門に説明会を開きました。
その上で、まずは実現性の高い小さな機能からスモールスタートし、段階的に機能を拡張していくという代替案を提示しました。技術的な制約とビジネス要求のバランスを取り、双方にとって納得のいく着地点を見つけることができました。
● プロジェクトの成功要因は何だと思いますか
私が考えるプロジェクトの成功要因は、第一に「目的とゴールの明確な共有」です。
プロジェクト開始時に、なぜこのプロジェクトをやるのか、何をもって成功とするのかを、チーム全員、そしてステークホルダーと合意形成することが最も重要だと考えます。
第二に、「オープンなコミュニケーション」です。良いことも悪いことも含め、情報が迅速かつ透明性高く共有されることで、問題の早期発見や、チームの一体感の醸成に繋がります。
この二つがしっかりしていれば、技術的な課題や計画の変更にも、チーム一丸となって柔軟に対応できると考えています。
6-2.技術選定・意思決定の質問6選
技術選定や意思決定に関する質問は以下の通りです。
- 技術スタックの選定で重視したポイントは何ですか
- レガシーシステムのモダナイゼーションに関わった経験はありますか
- 新技術導入時のリスク評価はどうしましたか
- パフォーマンス改善で実施した具体的な施策は何ですか
- 技術的な意思決定で失敗した経験はありますか
- アーキテクチャの変更を主導した経験はありますか
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
● 技術スタックの選定で重視したポイントは何ですか
プロジェクトの特性に合わせて重視するポイントは変わりますが、共通して重視するのは「プロジェクト要件との適合性」「エコシステムの成熟度」「チームの学習コスト」の3点です。
どんなに優れた技術でも、実現したいことやパフォーマンス要件を満たせなければ意味がありません。また、ドキュメントやライブラリが豊富で、コミュニティが活発な技術は、問題解決が容易で将来性も見込めます。
最後に、チームが迅速に価値を提供できるよう、既存のスキルセットや学習のしやすさも重要な判断基準です。
● レガシーシステムのモダナイゼーションに関わった経験はありますか
オンプレミスで10年以上稼働していたVB6製の業務システムを、Webアプリケーションとして刷新するプロジェクトに参加しました。
まず、現行システムの機能と業務フローを徹底的に分析し、新システムで本当に必要な要件を再定義しました。
そして、すべての機能を一度に置き換えるビッグバンアプローチはリスクが高いと判断し、業務ドメインごとに機能を分割して、段階的にリリースしていくストラングラーパターン(絞め殺しパターン)を採用しました。
これにより、リスクを分散させつつ、ユーザーからのフィードバックを早期に得ながら開発を進めることができました。
● 新技術導入時のリスク評価はどうしましたか
まず、その新技術が本当に解決したい課題に対して最適なのか、既存技術では代替できないのかを慎重に検討します。
その上で、技術の成熟度(安定バージョンか、破壊的変更の頻度は)、ドキュメントや事例の豊富さ、コミュニティのサポート体制といった技術的リスクを評価します。
次に、チームメンバーの学習コストや、市場における採用難易度といった人的リスクを考慮します。
最後に、影響範囲を限定した小規模なPoC(概念実証)を実施し、技術的な実現可能性やパフォーマンスを実証した上で、本格導入の判断を下します。
● パフォーマンス改善で実施した具体的な施策は何ですか
※この質問は職種別の質問と重複が多いため、プロジェクトのコンテキストをより具体的にして回答すると良い!
あるWeb APIのレスポンスが遅いという課題に対し、APMツールで分析したところ、特定のDBクエリがボトルネックであることが判明しました。
施策として、まずクエリの実行計画を見直し、適切なインデックスを追加しました。次に、アプリケーション側で発行されていたN+1クエリを、JOINを使った一括取得に修正しました。
最後に、更新頻度の低い関連データをRedisにキャッシュすることで、DBへのアクセス自体を削減しました。これらの施策により、APIの平均レスポンスタイムを80%改善することができました。
● 技術的な意思決定で失敗した経験はありますか
以前、あるプロジェクトで、当時流行していた新しいJavaScriptフレームワークを、十分な検証なしに採用してしまった経験があります。
当初は開発効率の高さに魅力を感じましたが、プロジェクトが進むにつれて、ライブラリのエコシステムが未熟で、必要な機能を実現するために多くのコードを自作する必要があることが判明しました。
また、日本語の情報が少なく、問題発生時のトラブルシューティングにも時間がかかりました。
この経験から、技術の流行に流されるのではなく、プロジェクトの要件や長期的な保守性を見据えて、慎重に技術選定を行うことの重要性を痛感しました。
● アーキテクチャの変更を主導した経験はありますか
モノリシックなアーキテクチャで開発されていたECサイトで、機能追加のたびに影響範囲の調査やテストに多大なコストがかかるという課題がありました。
私はこの課題を解決するため、マイクロサービスアーキテクチャへの移行を提案し、その設計を主導しました。まず、ビジネスドメインに基づいてサービスを分割する境界を定義し、サービス間連携のプロトコル(API、メッセージキュー)を設計しました。
そして、影響の少ない周辺機能から段階的にサービスとして切り出し、チームに成功体験を積んでもらいながら、徐々に移行を進めていきました。
6-3.チーム・組織での働き方の質問4選
チーム・組織での働きに関する質問は以下の通りです。
- 障害発生時のチーム内での情報共有はどうしていますか
- 他チームとの連携が必要な障害対応はどうしていますか
- 顧客影響を最小限に抑える障害対応はどうしていますか
- ポストモーテムの実施とチーム学習はどうしていますか
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
● 後輩や新入社員への技術指導で工夫したこと
一方的に教えるのではなく、相手に「考えさせる」ことを意識しています。まず、タスクの目的とゴールを明確に伝えた上で、具体的な実装方法はいったん本人に考えてもらいます。
行き詰まった際には、すぐに答えを教えるのではなく、「どういう選択肢が考えられる?」「それぞれのメリット・デメリットは何だろう?」といった質問を投げかけ、思考をサポートします。
また、ペアプログラミングを取り入れ、自分の思考プロセスを口に出しながらコーディングを見せることで、実践的なスキルや問題解決のアプローチを学んでもらうようにしています。
● リモートワークでの開発チーム運営の経験
フルリモートのチームで、コミュニケーションの質と量を担保することに最も注力しました。
毎朝のデイリースクラムで進捗と課題を共有するだけでなく、週に一度、雑談や最近気になっている技術について話す「雑談会」の時間を設け、偶発的なコミュニケーションを促進しました。
また、テキストコミュニケーションでは意図が伝わりにくいこともあるため、少しでも疑問があればすぐにハドルなどで声かけをすることをチームのルールとしました。
設計などの複雑な議論は、オンラインホワイトボードを使い、図を書きながら行うことで認識齟齬を防ぎました。
● 他部署との技術的な調整や説明の経験
マーケティング部門から、顧客データを分析基盤に連携してほしいという依頼がありました。私はまず、マーケティング担当者が「最終的に何を実現したいのか」という目的を深くヒアリングしました。
その上で、データベースの構造やAPIの仕様といった技術的な詳細を、専門用語を使わずに、業務フローに沿った形で説明しました。
どのデータを、どのタイミングで、どのような形式で連携できるのか、そして技術的な制約は何かを明確に伝えることで、双方の認識を合わせ、スムーズにプロジェクトを進めることができました。
● 開発プロセスの改善に主体的に関わった経験
以前のチームでは、コードレビューが形骸化し、品質の低いコードがマージされることが問題となっていました。
私はこの状況を改善するため、まずチームでレビューの目的(品質向上、知識共有など)を再確認する場を設けました。その上で、プルリクエストのテンプレートを導入し、変更の概要やテスト内容を記述するようにルール化しました。
また、「LGTM」だけのレビューを禁止し、必ず一つは具体的なコメントをするように働きかけました。この取り組みにより、レビューが活性化し、チーム全体のコード品質が向上しました。
7.エンジニア面接の効果的な練習法3選
エンジニアの面接は練習を繰り返し行うことで、本番で焦ることなく落ち着いて回答できます。ここからは効果的な練習法を3つ紹介します。
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
7-1.鏡の前で表情を見ながら練習
鏡を見ながら面接の練習をすることで自分の表情や仕草をチェックできます。
面接官に与える印象は表情や仕草によって大きく左右され、日頃から出るクセは無意識にでてしまうことも多く、面接では注意しなければいけません。
そのため、鏡の前で自己紹介や質疑応答の練習を行い、明るい表情と適度なジェスチャーを心がけてください。
例えば、時間が経つにつれて表情が硬くなるクセがあるなら明るい表情を心がけ、単調な話し方をしてしまうクセがあれば、ジェスチャーなどを入れてリズムを作ったりする必要があります。
毎日10分程度でも、鏡の前で面接練習を行い表情や仕草の改善を続けることで面接で練習の成果を発揮できます。
また、話す内容を覚えるだけでは不十分で面接本番になると「緊張で上手く発言できない」「クセがでてしまう」人もいます。相手にどのように映っているのかまでを確認するのが面接対策です。
7-2.オンラインなら録画機能を活用
最近は対面ではなくオンラインでの面接も一般化されています。オンライン面接の場合、録画機能を使用して自分の受け答えを客観的に評価してみてください。
自分の受け答えを見直すことで、改善点に気づきやすくなるためです。
Zoomなどのビデオ会議ツールの録画機能を使い、模擬面接を録画します。その後、録画した模擬面接を見直し、言葉遣いや話し方、表情などをチェックし改善点をリストアップします。
また、以下のことは必ず確認するようにしてください。
- 頭の先から肩までしっかりと映っているか
- 画面と自身が近すぎず遠すぎないか
- ネット環境は悪くないか
オンラインの場合は、カメラ位置が大きく影響します。自身の話している様子やスピードなど事前に把握しておくことで、改善点を見つけられます。
録画機能を使用すれば、同じ部分を何度も再生できるため苦手な受け答えを重点的にチェックし、反復練習を行えば自信を持てるようになります。
7-3.家族や友人等の第三者のフィードバック
家族や友人に模擬面接をしてもらい、フィードバックをもらうことが面接では効果的です。面接というのは結局のところ、「自分ができた」ではなく「どう見られたか」になります。
そのため、第三者目線のフィードバックが非常に重要なのです。
家族や友人等の第三者の視点から自分では気づかない改善点を指摘してもらうのが、面接が苦手な人にとって特にやるべきことになります。
「鏡の前で練習する」「録画機能を使用する」なども効果的ですが、改善すべき点を全てを見極めるのは難しいです。また、自分では正しいと思っていても第三者から見れば間違っているといった発言や仕草にも気づくことができます。
家族や友人に面接官役を依頼し、模擬面接を実施します。終了後には必ずフィードバックをもらいます。また、1人だけでなく複数の人に模擬面接をしてもらい様々な視点からのアドバイスを参考にしてください。
ただし、家族や友人など面接のプロではない方だと「ん~。いいんじゃない?」みたいな、的確なフィードバックをもらえない可能性があります。
また、「面接が苦手で知り合いに見られたくない」といった方や「近くに友人や家族がいなくて実践が難しい」という状況はよくあります。
もし、当てはまる状況にあるのであれば、ユニゾンキャリアのITエンジニア特化の転職支援サービスをご利用ください。
8.エンジニアの転職はユニゾンキャリア
「なかなか面接を通過できない」「あまりできが良くないのになぜか通過してしまった」そんな時はユニゾンキャリアの転職支援サービスをご利用ください。
もしかすると、思わぬ落とし穴にはまっているかもしれません。
こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】
8-1.ユニゾンキャリアのサービス特徴
ユニゾンキャリアはIT・WEB業界に特化した転職支援サービスを行っております。
IT業界に精通した専任のアドバイザー全員がエンジニアのキャリアプランから面接対策、入社後のサポートまで徹底して行います。
面接対策など、Googleの口コミ「★4.8」の高い評価をいただいておりますので、安心してご相談いただければと思います。
口コミ評価
転職を無理強いすること・サポートを割愛することはありません。ユニゾンキャリアではIT業界経験者の方でも面接から内定後のサポートまで真摯に対応いたします。
転職活動を進めるにあたって少しでもお悩みごとありましたら、お気軽にお問い合わせください。ご相談から内定まで「完全無料」でご利用いただけます。
8-2.ユニゾンキャリアの転職成功事例

成功者インタビューより
ー転職しようと思ったきっかけを教えてください。
前職は給与面の不満から転職をしようと決意しました。
給与は自身のモチベーションや生活にも関わるので、1番のキッカケです。
ただ、何の考えや準備もなく「年収をあげたいから転職しよう!」と思ったのではなく、ユニゾンキャリアの担当者様からエンジニアのキャリアアップの流れと、年収の上げ方について詳しく説明を受け、転職活動をスタートしました。
ー自分のスキルに不安を感じていたようですが、面接などへの不安はありましたか?
面接は問題なくできました。
というのも、担当者の方に「この会社はここが売りなんで、ここを準備しておきましょう」と細かく指示をいただいていたので、どう答えればいいかわからない状況にはなりませんでした。
ーキャリアアップ転職の結果はいかがでしたか?
選考は4社受けて、全ての企業から内定をいただきました。
4社ともすべて上流工程の案件だったので、確実に年収が上がる企業ばかりで内定が出た時は素直に嬉しかったです。また、自分の市場価値が高いことを実感しました。
エンジニアの転職で上手くいかない場合は、1人で悩まず、ぜひ弊社までご相談ください。
ご相談から内定まで「完全無料」でご利用できます。